ふと思ったんです。
常に情報にさらされて脳が休まらない私たち。
非効率だと思えていた無駄なことこそ、現代には実は必要なのかもしれないな…と。
私たちの生活は、スマホを中心に大きく変わりました。
便利さの一方で、気づけば一日中スクロールし続け、脳が常に働き詰めになっている──。意識していないのだけれども、ショート動画を観てしまったり、意味もなくSNSを眺めてしまったり。
「なんだか疲れる」「何もしていないのに、ずっと落ち着かない」。
その背景には、“余白のない暮らし”による脳の慢性的な疲労があるといわれています。
そんな今こそ思い出したいのが、平成初期の小学生たちが過ごしていたあの「夏休み」の風景。どこかノスタルジックな色合いの昔の風景。
朝のラジオ体操、絵日記、朝顔の観察、予定のない長い午後──そこには、現代人が失いかけている“脳が休まる生活リズム”のヒントが詰まっていました。
本記事では、スマホによる脳疲労や情報過多に悩む現代人に向けて、平成初期の夏休みにあった「自然な脳のケア習慣」を科学的視点から再構成し、今の私たちに再現できる“余白のある暮らし”として提案していきます。
スマホ疲れする私たちに、足りないもの

いつの間にか、スマホは生活のあらゆる瞬間に入り込んでいます。仕事の連絡、情報収集、SNSのやり取り、空いた時間の暇つぶし──気づけば一日中、画面を見て過ごしてしまっていたという日も珍しくないでしょう。
ところが、そうした生活のなかで「なんだかずっと疲れている」「休んでいるはずなのに頭が休まらない」と感じる人が増えています。それは単なる気のせいではありません。
近年では、「スマホ認知症」や「脳の情報疲労」といった言葉で、デジタル機器によって休む暇を失った脳の状態が注目されています。
脳は“情報の洪水”に耐えられていない
スマホは、私たちの認知機能に絶えず負荷をかけています。新しい通知、次々と切り替わる画像や動画、速すぎる情報の流れ──それらはすべて、脳の「ワーキングメモリ」を使い続ける要因です。
本来、人の脳は「休む時間」と「働く時間」を切り替えることでバランスをとっています。しかし、スマホが常に手の届くところにある現代では、“オフになる時間”がほとんど存在しないのです。
「疲れているのに、うまく休めない」現代人の矛盾
休日にぼんやり過ごしても、どこか落ち着かない。夜寝る前に無意識にスマホを手に取ってしまう。トイレやお風呂にもスマホを持ち込んでしまう。そんな経験は、まさに「情報との距離の取り方」を失った結果といえるでしょう。
そして、これは単なる個人の問題ではなく、社会全体が抱える“生活リズムのゆがみ”に関係しているのです。
脳が本当に休まるには、「情報を遮断する」だけでなく、自然な形で余白が生まれる生活構造が必要です。そのヒントとなるのが──平成初期の夏休みです。
次のセクションでは、その夏休みの風景がどのようなものであり、なぜそれが脳にとって理想的だったのかを見ていきます。
平成初期の小学生の夏休みを思い出す

今から30年ほど前、平成の初期に子ども時代を過ごした世代にとって、夏休みは特別な季節でした。
日常から解放された自由な時間のなかに、どこか規則正しいリズムがあり、何もしない時間も不思議と充実していた──そんな記憶を持っている人も多いのではないでしょうか。
『夏休みの友』という名前でありながら、子どもたちの夏休みの敵となっていた宿題なんかもあったり。
朝はラジオ体操から始まる
近所の公園に集まり、出席カードを首から下げて、6時半の音楽とともに体を動かす。たった10分の出来事ですが、朝日を浴びて体を起こすリズムは、1日の心身のコンディションを整えるうえで非常に理にかなっています。
地域の人たちとのコミュニケーションのきっかけにもなっていましたね。
「予定のない時間」が日常にあった
午前中に宿題を済ませたら、午後は何をするとも決まっていない。家で絵を描く、近所の空き地で遊ぶ、セミの声を聞きながら昼寝をする──誰にも邪魔されず、何かをしなければならないプレッシャーもない時間が、自然と流れていました。
この“目的のない時間”こそが、現代に失われつつある「余白」の象徴です。
当時は今ほどエアコンが普及していなかったこともあって、涼しい午前中に宿題に手を付ける、といった習慣があったんですよね。もちろん、時間管理は人それぞれではありましたが。
アナログな活動が脳にやさしかった
夏休みの宿題といえば、絵日記、読書感想文、漢字練習、朝顔の観察記録、自由研究など。どれも手で書き、観察し、試行錯誤するものばかりでした。テレビやゲームの時間は制限されており、「退屈」が日常の一部として許容されていたのです。
今思えば、デジタルに依存しない“手間のかかる営み”が、脳のリズムを自然と整えていたのかもしれませんね。
では、なぜこのような生活が、脳にとって良かったのでしょうか。
次のセクションでは、「平成初期の夏休み」がもたらしていた脳の安定効果を、心理学や神経科学の視点から掘り下げていきます。
なぜ、あの夏休みは脳に良かったのか?

平成初期の夏休みには、特別な仕掛けがあったわけではありません。それでも、あの頃の生活には確かに「なんだか疲れる」「何もしていないのに、ずっと落ち着かない」といった漠然とした感覚はありませんでした。これは単なる思い出補正ではなく、脳のしくみに合った自然な生活構造がそこに存在していたからです。
内省と創造を支える「ぼーっとする時間」
脳には「デフォルトモード・ネットワーク(DMN)」と呼ばれる内省的な活動ネットワークがあります。これは、何かに集中していないときに活性化し、創造性の発揮や記憶の整理、自分自身の感情の把握に深く関係しています。
夏休みの中で、何をするともなく空を眺めたり、ぼんやり虫を見つめたりしていた時間──それは、DMNが活性化する「脳のメンテナンスタイム」となっていたのです。

規則と自由のバランスが取れていた
「朝は決まった時間にラジオ体操へ行く」「宿題を済ませたら自由に遊べる」──このような生活は、規則的なリズム(コントロール感)と自由(選択感)の両方を子どもに与えていました。
この“適度な自由の中にある秩序”は、心理的にも非常に安定をもたらす要因となります。大人にとっても、ルーティンがありながらもプレッシャーの少ない生活は、ストレスを軽減し、脳の回復を促します。
情報の「密度と速度」がちょうどよかった
当時は、テレビも限られた時間しか観られず、情報の取得は本や人との会話が中心でした。情報は遅く、限られていて、処理する余裕がありました。今のように数秒ごとに刺激が入れ替わるSNSとは対照的です。
つまり、脳にとって過剰ではない刺激量だったことも、休息の質を高めていたといえるでしょう。
こうして見ていくと、あの夏休みは単なる「懐かしい風景」ではなく、現代人が無意識に求めている“回復のリズム”そのものだったことが分かります。
次のセクションでは、スマホ認知症や情報疲労といった現代の問題と、どのように対比されるのかを掘り下げていきます。
スマホ認知症と脳疲労の現代的課題
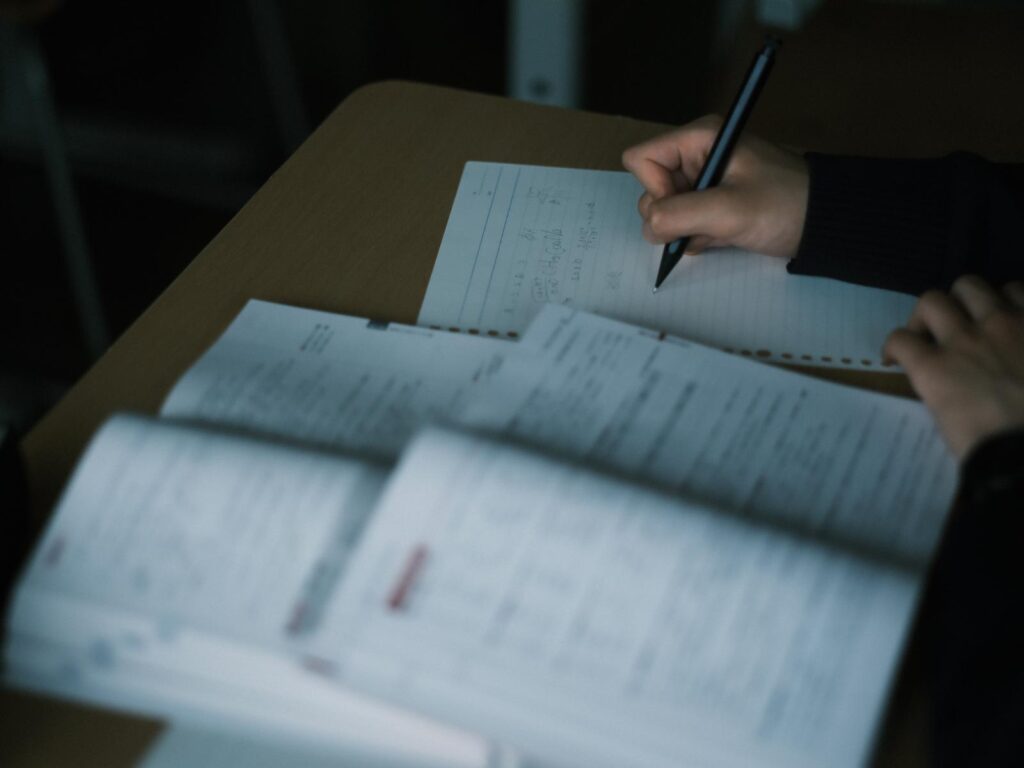
かつての夏休みにあった「余白」が失われた一方で、現代の生活は“つながりっぱなし”の状態が当たり前になりました。特にスマートフォンの普及は、私たちの脳に常時アクセスされることを許し、休息のタイミングすら見失わせています。
この環境が引き起こす代表的な問題が、いわゆるスマホ認知症です。
「スマホ認知症」とは何か?
スマホ認知症とは、医学的な正式名称ではないものの、近年注目される概念です。スマホの過使用によって次のような症状が起こる状態を指します。
- 物忘れが増える(短期記憶の低下)
- 集中力が続かない
- 感情のコントロールが効かない
- 常に気が散っている感覚がある
背景には、脳のワーキングメモリ(短期的な情報処理領域)への過剰な負荷があります。通知、情報の切り替え、マルチタスク──こうした刺激は脳を酷使し、回復の機会を奪います。
“空白時間の消失”がもたらすもの
現代では、何もしていない時間がほとんど存在しません。
待ち時間や移動中、トイレの中、寝る直前──どんな場面でもスマホを見てしまう。これにより、脳が「ぼーっとする」時間が失われてしまったのです。
結果として、脳は情報処理を止める暇もなく、慢性的な疲労状態に陥ります。
これは単なる「気分の問題」ではなく、認知機能の低下や情緒の不安定さにつながる重大な問題です。
情報の質ではなく「量と速さ」が問題
現代の情報には、質的に優れているものも多くあります。問題なのは、それが絶え間なく、スピーディーに流れ続ける環境です。人の脳は一度に処理できる情報量に限界があるため、過剰な情報刺激は認知資源を消耗させ、疲労だけが蓄積していきます。
このような環境下で、ただ「スマホをやめよう」とするだけでは不十分です。必要なのは、脳が自然と回復できる“生活の設計”そのものを見直すこと。
次のセクションでは、平成初期の夏休みをヒントに、現代でも再現可能な脳ケアの具体策を紹介していきます。

いま再現できる「夏休みの脳ケア」

現代の生活をすべて平成初期のように戻すことはできません。
しかし、あの夏休みにあった「脳が休まる習慣」は、工夫次第で日常に取り入れることが可能です。ここでは、無理なく始められる再現方法をいくつか紹介します。
朝の“ラジオ体操的リズム”をつくる
あの時代、1日はラジオ体操で始まっていました。朝日を浴びながら身体を動かすことで、自律神経が整い、体内時計もリセットされます。
現代では、ラジオ体操にこだわらずとも、軽いストレッチや5分の散歩で十分。
起き抜けにスマホを手に取る代わりに、まずは身体にスイッチを入れることが、脳にとっても効果的です。


「観察」と「記録」で脳に余白を
朝顔や植物の育成日記、自由研究、絵日記──子どもの頃のそれらは、単なる宿題以上に、観察し、考え、記録するという行為を日常化させていました。
現代でも、観葉植物や発酵食品、天気の変化など、身の回りには観察できるものが豊富にあります。
それを手書きで記録する習慣は、脳の働きを整えると同時に、感覚を取り戻す時間にもなります。


“スマホなし時間”を意識的に設ける
1日すべてをアナログにするのは非現実的ですが、「この1時間だけはスマホを見ない」と決めることは可能です。
たとえば、食後の時間や寝る前30分など、“余白を取り戻す時間帯”を意図的に設定しましょう。
初めはそわそわするかもしれませんが、しばらくすると、情報から離れたときの深い呼吸と静けさがむしろ心地よく感じられるようになります。

手でつくる、触れる、動かす
工作、料理、掃除、簡単な手芸など、手を使う行為は脳の感覚野や運動野をやさしく刺激します。
スクリーンを通さない、手間のある作業こそ、脳にとって“適度な刺激と休息”のバランスになります。
平成初期の夏休みにあった生活の多くは、「やらなければならないもの」ではなく、自然と生活に組み込まれていた“脳の回復装置”だったといえるかもしれません。
次のセクションでは、こうした発想を単なる懐古に終わらせず、今の暮らしにどう生かすか──その考え方を掘り下げていきます。
子ども時代に戻るのではなく、「余白のある生活」へ

ここまで見てきたように、平成初期の夏休みには、現代の私たちが忘れかけている「脳の自然な休め方」が随所に存在していました。とはいえ、この記事が伝えたいのは、懐かしさに浸ることでも、子ども時代をそのまま模倣することでもありません。
大切なのは、あの頃の生活に含まれていた“構造”や“質感”を現代の暮らしに応用する視点です。
懐古ではなく“翻訳”としての夏休み的生活
今の私たちは、情報も環境も、働き方も当時とはまったく違う状況にいます。その中で大人がラジオ体操カードを首から下げたり、毎日朝顔を育てたりすることは現実的ではないでしょう。
ですが、「朝に身体を動かす」「記録する習慣を持つ」「手を動かす作業を取り入れる」といった“行動の本質”を抜き出して翻訳することは可能です。
つまり、
懐かしい過去をそのまま再現するのではなく、今の生活に合う形で“設計し直す”こと
この姿勢こそが、現代人の脳疲労に対して有効なアプローチとなります。
“余白”は削られるものではなく、設計するもの
スマホを使うことが悪いのではなく、それにすべての空白時間を奪われていることが問題なのです。
そして、空白とは「何もしていない時間」ではなく、意識的に余白を許す設計そのものです。
忙しいからこそ、「ここだけは手を動かす」「この時間だけはスマホから離れる」と決めることで、私たちは現代の中に“夏休み的な構造”を取り戻せるのです。
まとめ:脳のための、生活の設計図を見直す
情報に囲まれ、画面と向き合い続ける現代の私たちは、常に「何かを処理している脳」で過ごしています。
しかしながら、本来脳には、何もしない時間、手を動かして考える時間、そして、ゆっくりと感覚を取り戻す時間が必要です。
平成初期の小学生が過ごしていた夏休み──
それは、懐かしさ以上に、脳にとって自然で無理のないリズムが組み込まれた生活構造だったと言えるでしょう。
ラジオ体操で1日を始め、植物を育て、絵日記を書き、空き時間は思いっきり遊んだりぼーっとしたりする。
これらはすべて、脳科学の視点からも有効な「回復の技術」として再評価できるものです。
もちろん、当時の暮らしをそのまま再現することはできません。
しかし、“余白のある生活”という考え方を取り入れることは、スマホ社会を生きる私たちの脳にとって、必要な選択肢のひとつと言えるでしょう。
あの夏の日のように、少しだけ手を止めて、空を見上げてみる。
そんな時間を、日々の中に取り戻してみませんか。


よくある疑問と対処法(FAQ)
ここでは、「夏休み的な生活リズムを取り入れたいけれど難しそう」と感じる方に向けて、想定される疑問や不安に先回りしてお答えします。
手書きや観察が苦手です。効果はありますか?
苦手意識があっても大丈夫です。
目的は「うまくやること」ではなく、“手を動かしながら、情報の処理スピードを落とすこと”にあります。
字が汚くても、記録が続かなくても問題ありません。「観察しよう」という意識を持つだけで、脳はいつもとは違う働き方を始めます。
朝にラジオ体操や散歩をする時間がとれません。
無理に早起きする必要はありません。
「毎日同じタイミングで5分間、体を動かす」という習慣でも十分に効果があります。
スマホを見ない時間を作ると、かえってそわそわします。
それは「慣れ」の問題です。
現代の脳は、“常に刺激がある状態”に慣れすぎています。だからこそ、最初は落ち着かないのです。
まずは「1日10分だけスマホを置く」など、ごく短い時間から始めましょう。
習慣化すれば、逆に「スマホなしの時間のほうが落ち着く」と感じるようになります。
子どもがいない・独身だと、夏休み的な雰囲気は作れませんが?
雰囲気ではなく、「構造」を作ることが大切です。
夏休みの本質は、余白のある構造と、情報に追われない時間感覚にあります。
それは年齢やライフスタイルに関係なく設計できます。むしろ、大人だからこそ、自分に合わせた“夏休みの再構築”が可能なのです。
どの項目も完璧にこなす必要はありません。大切なのは、少しずつ生活に“余白”を取り戻す意識です。
.webp)








