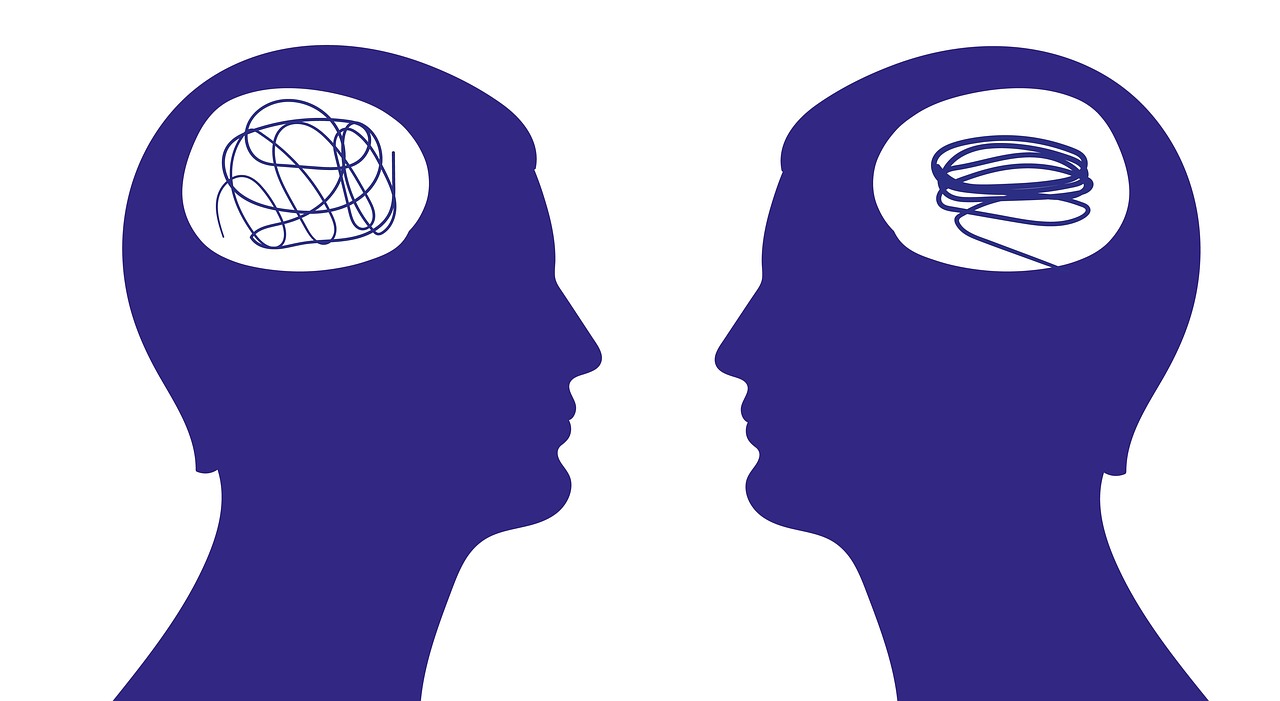「なぜか毎日ぐったりする」「職場の空気が重たい気がする」「頑張っているのに報われない」──そんな漠然とした“モヤモヤ”を抱えながら働いていませんか?
職場で感じる違和感やしんどさは、自分の弱さなどとは関係がないかもしれません。
産業・組織心理学は、働く人の行動や感情を「職場という構造」から読み解く学問です。個人では変えにくい問題を、“構造の見直し”という視点で捉え直すことで、抱えていた重さが軽くなることがあります。
この記事では、産業・組織心理学の基本から、職場のモヤモヤを“自分ごと”だけで終わらせないための視点、そして日々の働き方に取り入れられる実践ヒントまでをご紹介します。
「自分のせい」と思い込む前に。
まずは、今の職場にある“構造のクセ”を、一緒に見つめ直してみませんか?
職場のモヤモヤは「構造」からもやってくる
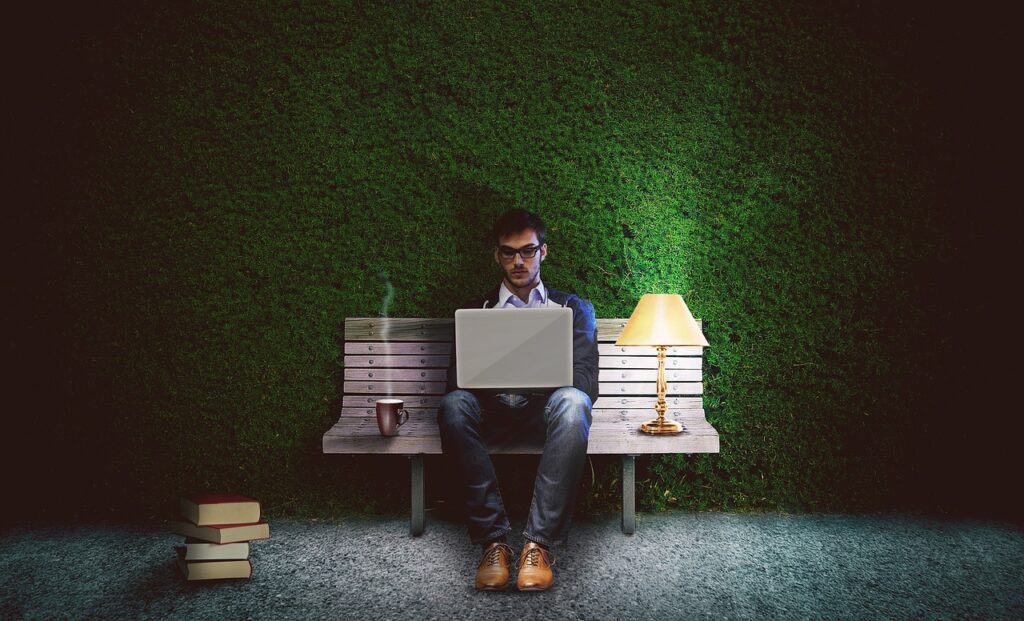
職場で感じるストレスやモヤモヤは、必ずしも「人間関係が悪い」や「自分が弱い」といった“個人”に原因があるとは限りません。
むしろ、産業・組織心理学の視点では、「職場という構造」が私たちの行動や感情に大きく影響していると考えます。
このセクションでは、「構造」の視点がなぜ重要なのか、そしてそれがどのように私たちの働き方や気持ちに影響しているのかを、具体的に見ていきます。
「構造」とは、個人より大きな“空気の土台”
ここでいう「構造」とは、ルールや制度、役割分担、評価の仕組み、人の流れ、情報の伝わり方など──個人の振る舞いを形づくる“土台”のことです。
たとえば、明確な指示がないまま丸投げされるのは「業務設計の構造」に問題があるかもしれません。
「どうせ言っても変わらない」という諦めは、「意見が届かない組織構造」の顕れです。
構造は、見えにくくても確実に、その組織内で働く人の立ち居振る舞いに影響を及ぼしています。
「個人のせい」にすると、構造の問題が見えなくなる
「私の頑張りが足りないのかな」「なんでうまくできないんだろう」など。
そうやって、構造の問題を“個人の性格や能力のせい”にしてしまうと、本当の改善ポイントが見えなくなってしまいます。
産業・組織心理学では、“人”だけを責めるのではなく、“場”や“仕組み”側に目を向けることで、より建設的な解決策が見えてくるものと考えます。
「変えられないもの」に気づくと、力を注ぐ場所が変わる
すぐには変えられない構造もあります。しかし、それが“見えている”かどうかで、自身の消耗度合いは大きく変わります。
たとえば、「この部署は評価基準が曖昧なんだ」と気づくだけでも、「なぜ頑張っても報われないのか」が自分の価値ではなく“仕組みのせい”だと理解できるようになります。
そのうえで、「では、自分はどこで力を注ぐか?」を冷静に見直すことができるようになります。
職場で感じるモヤモヤや息苦しさには、「個人」ではなく「構造」に原因があることがあります。構造を意識することで、自分を責めすぎず、冷静に働き方を見直すことができます。
次のセクションでは、産業・組織心理学が重視する“構造を見るための視点”を紹介していきます。
構造を見る“4つの視点”──産業・組織心理学が教えてくれること

「職場の構造」といっても、何をどう見ればよいのか、最初はイメージがつきにくいかもしれません。
産業・組織心理学では、個人の行動や感情の背景にある“構造”を理解するために、いくつかの視点を活用しています。
ここでは、実際に職場を見るときに使える4つの代表的な視点を紹介します。
どれも、ちょっとした「見方のスイッチ」として、身近な職場環境に応用できるものです。
役割の視点:誰が何をどこまで担うのか?
「それ、自分の仕事?」と感じたことがあるなら、それは“役割の構造”があいまいな職場かもしれません。
誰が何を、どの範囲まで担うのかが不明確だと、仕事の境界があいまいになり、責任の所在も不透明になります。
「全部抱え込んでしまう人」「いつも指示待ちになる人」が生まれるのは、構造の問題であることが多いのです。
情報の視点:何が、どこまで、どう伝わるか?
「知らなかった」「聞いてない」──そうした行き違いが多い職場では、“情報の流れ”という構造に目を向けてみましょう。
情報が一部の人にしか届かない、口頭だけで伝わる、言いにくい空気がある……。
こうした“情報の非対称性”は、無意識の分断や不信感を生む大きな原因になります。
評価の視点:何が評価され、何が無視されているか?
人は“見られている軸”に沿って振る舞います。
だからこそ、「評価の仕組み」は組織の行動文化をつくる根っことなります。
たとえば、「売上だけが評価される職場」では、チームワークや育成への貢献は軽視されやすくなります。
逆に、「曖昧なまま評価される職場」では、努力しても報われない不公平感が募っていきます。
暗黙のルール:言葉にされない“前提”が行動を縛る
「こうするのが当然」「言わなくてもわかるだろう」
こうした“言葉にされないルール”が、職場にある空気や行動を無意識に縛っていることもあります。
たとえば、「定時に帰っていい雰囲気じゃない」「上司の機嫌を取らないと動きづらい」など、組織の“文化”や“風土”が働き方に与える影響は非常に大きいのです。
産業・組織心理学では、こうした構造的な視点を通して、働く人の行動や気持ちを理解しようとします。
どれも難しい分析ではなく、「見方の枠組み」を変えるだけで、今まで気づかなかった“構造”が見えてくるようになります。
次のセクションでは、こうした構造の見方を踏まえたうえで、実際にモヤモヤをどう整理し、行動の選択肢を持つかを考えていきます。
モヤモヤの正体を整理する──自分の「しんどさ」を構造でとらえる

「なんとなくつらい」「気づくと疲れ果てている」
そうした職場でのモヤモヤは、言葉にしづらいからこそ放置されがちです。ですが、それを「自分の弱さ」や「甘え」だと決めつけてしまう前に、構造的な視点で見直すことで、新しい整理の仕方が見えてきます。
このセクションでは、自分のモヤモヤを“構造”としてとらえるためのステップを紹介します。
その「しんどさ」は、個人のせい?
職場でのつらさや違和感は、つい「自分がうまくやれてないから」と思いがちです。
しかし、その原因が「評価が不透明」「役割が曖昧」といった組織の仕組みに起因することは少なくありません。
たとえば、「毎日遅くまで残ってしまう」のは、本人の時間管理の問題ではなく、「無言の同調圧力」や「業務配分の偏り」かもしれないのです。
「疲れ」の背景にある構造を問い直す
心が疲れているとき、ただの“忙しさ”ではなく、“報われなさ”や“矛盾”が根底にある場合があります。
それは、「成果が見えにくい仕事が軽視される」「助けを求めづらい空気がある」など、制度や文化に潜む構造的な問題です。
“どんな時に疲れるのか”“なにに怒りを感じているのか”を手がかりに、背景の構造を見つめ直してみましょう。
「こうあるべき」から自由になる
「上司とはこう接するべき」「やる気があるなら残業は当たり前」
──そんな“べき論”に無意識に縛られていないでしょうか?
実は、それらの多くは職場に根づいた“暗黙の構造”であり、絶対的な正解ではありません。
一度その前提を疑い、「本当にそうする必要があるのか?」と問い直してみるだけでも、息苦しさは軽くなることがあります。
モヤモヤを「自分の感情」として抱え込むのではなく、「構造の中で起きていること」として整理することで、少しずつ見え方が変わります。それは、問題の“責任転嫁”ではなく、自分がこれからどう関わっていくかを考えるための下準備です。
次のセクションでは、そうした視点を踏まえて、「どう行動するか」「自分にできる範囲で何ができるか」を考えていきましょう。
構造を知ったうえで、“自分にできること”を見つける

モヤモヤの正体が「自分の内面」だけでなく「職場の構造」にあると見えてきたとき、次に悩むのが「じゃあ、自分には何ができるんだろう?」という問いかもしれません。
職場全体の仕組みをすぐに変えることは難しくても、自分自身の見方や行動の仕方を少し変えることで、影響を及ぼせる範囲が広がることもあります。このセクションでは、構造を理解したうえで、自分のペースで試せる「動き方のヒント」を紹介します。
“語れるようにする”だけで、見えてくるものがある
気持ちや違和感を、整理して言葉にしてみる。それだけでも「自分が何につまずいているのか」が見えやすくなります。
たとえば、「なんだか疲れる」ではなく「成果が見えづらいタスクが多くて評価されにくいのがつらい」と言語化できれば、周囲への相談や見直しも具体的に動きやすくなります。
「うまく言えない」が当たり前のスタートです。
誰かに話すためではなく、自分のために言葉にしてみること。それが一歩目です。
小さな“働きかけ”が、空気を変えることもある
構造を知ったからこそ、「自分だけが変わっても無意味」と感じることもあるかもしれません。
ですが、たとえば「ありがとう」と一言添える、タスクの見える化を提案するなど、小さな行動から職場の空気が少し変わることもあります。
“仕組みそのもの”を変えようする必要はありません。「安心して言える雰囲気をつくる」「対話の姿勢を持つ」といった行動も、立派な構造への働きかけです。
“自分を守るための線引き”も大切な行動
何でも受け入れることが良いわけではありません。「ここまではできるけど、これ以上は難しい」と線引きすることも、健全な関係を保つうえで欠かせません。
たとえば、「週に一度は定時に帰る」「業務外の連絡にはすぐ返信しない」といったルールを、自分の中で静かに設けてみるだけでも、心身の消耗は抑えられます。
それは、職場への反抗ではなく、長く働き続けるための自分なりの“構造調整”ともいえます。
言語化ができれば次のアクションが取れる
職場の構造がわかったうえで、その問題が解消する見込みないのであれば、転職を視野に入れたりすることもできます。または、うまく手を抜きつつ、必要な仕事だけをきっちりとこなすという静かな退職のような働き方もできるかもしれません。
ストレスを抱え込み過ぎないことが大切です。
職場の構造に目を向けることは、「すべてを変える」ためではなく、「自分の働き方を見直す」ための視点でもあります。ほんの少しでも「自分にできること」が見つかると、モヤモヤはただの“しんどさ”ではなく、“問いかけ”に変わっていきます。
次のセクションでは、ここまでの内容をふり返りながら、改めて「働くこと」と「構造を見直す視点」について、まとめていきます。
まとめ|「自分のせいだけじゃない」と気づくことが、構造を見直す第一歩
職場で感じるモヤモヤやしんどさの正体は、「自分が弱いから」でも「気にしすぎ」でもありません。
それは多くの場合、組織の仕組みや関係性のあり方など、“構造”の中に潜んでいます。
本記事では、産業・組織心理学の視点を手がかりに、
- 職場の違和感の背景にある「構造」という視点
- 見えにくい仕組みをとらえるためのヒント
- 自分のペースで始められる小さな実践
を通じて、「職場のモヤモヤ」を個人の問題に留めず、より立体的に捉える方法を見てきました。
構造に目を向けることは、自分を守るための目を持つということでもあります。
すぐに解決できなくても、「仕組みのせいかもしれない」と気づけるだけで、自分を責める力が格段に和らぐはずです。
そしてその気づきが、「じゃあ自分には何ができるだろう?」という小さなアクションにつながっていきます。
まずは、自分の感じていることを大切にしながら、「働き方のなかの構造」を見直したり、自分にとって最善と思える行動をとってみるところから始めてみてください。


よくある質問
モヤモヤの原因が“構造”にあるって、どうやって見分ければいいですか?
まず、「誰か特定の人が悪いわけではないのに、状況がずっと改善されない」と感じる場合は、構造的な問題が関わっている可能性が高いです。
たとえば、「制度が現場に合っていない」「役割分担があいまい」「心理的安全性が確保されていない」など、個人の努力ではどうにもならない要因が隠れていることがあります。
自分のせいにする前に、「そもそもこの環境でやっていける設計になっているのか?」という視点を持ってみてください。
上司や同僚とうまくいかないのも“構造”のせいなんですか?
人間関係における摩擦も、多くは「関係性の構造」に根ざしています。
たとえば、意見を言えない空気、暗黙のルール、曖昧な上下関係などは、個人よりも職場全体の文化や枠組みによって形づくられています。
もちろん個々の相性や感情も影響しますが、「どうしてそうなっているのか?」を一段深く掘り下げると、“構造のひずみ”が見えてくることがあります。
自分にできる小さな一歩って、どんなことですか?
たとえば、
- 会議で無理に発言しようとせず、「どう聴くか」に意識を向ける
- 疑問や違和感を“そのままメモに残す”習慣をつくる
- 周囲とのやりとりで「その役割は本当に自分の責任か?」と一呼吸置く
- 組織を見限って転職してしまう
など、「無理に変えようとしないけれど、流されすぎない」行動が小さな一歩になります。
行動よりも先に“視点”を変えることが、結果的に自分の働き方を少しずつ整えることにつながっていきます。
.webp)