長いこと会社へ尽くして来たけど、最近なんかやる気でないなー。
仕事に全然集中できないなー。
尊敬できる人も居ないし、成長も実感できないし、そろそろ潮時かな…。
なんて思っていたりしませんか?
ここでは、漠然と「退職したいなぁ」と思い始めたそんなあなたへ、私の体験談から退職前にやっておくと良いことをお伝えしたいと思います!!ぜひ、ご参考ください。
この記事が少しでも皆さまのお役に立てましたら幸いでございます。
退職を視野に入れたらやっておくと良いこと。(ただし、個人の経験談入ってます)
やっておくと良いことリスト
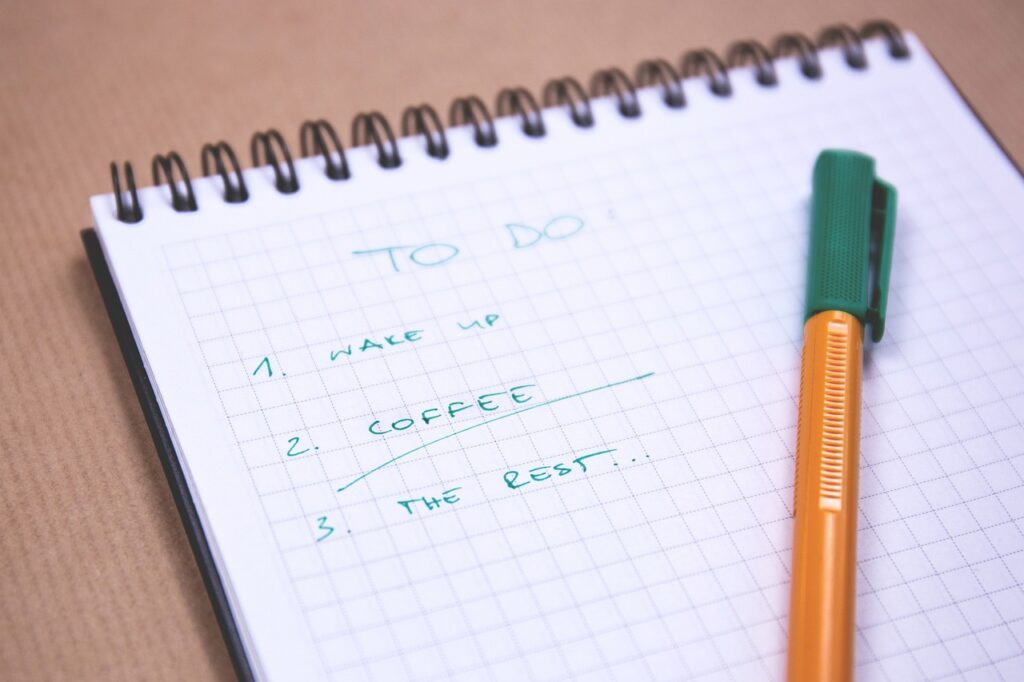
退職を視野に入れたらやっておくと良いことリストです。
- 退職後にどうするかを決める
- 必要な生活費を計算する
- 生活防衛資金を貯める
- FP3級の知識を入れておく
- 副業を育てるor副業への投資を済ませておく
- 会社の福利厚生のポイントがあれば使っておく
- 就業規則や給与規則などに目を通す
それでは、詳しく見ていきましょう。
1.退職後にどうするかを決める
漠然と退職したいなぁ…と思い始めたら、辞めた後にどうするかをじっくり考えておきましょう。「転職する」「ちょっとゆっくりする」「起業する」とかとか。具体的な構想があったほうが良いのでしょうが、バクっと方向性だけでも決めておくと良いと思います。
働きながら転職先を見つける場合には、あまり役には立ちませんが、ここで考えた方向性で今後必要になってくる生活防衛資金が変わってきます。私の場合はもう会社での仕事も面白くないし、なんか朝早く起きて通勤するのが辛かったので、(会社に依存せずに)一人でも生きていけるようになりたい!っていうそんな理由でした。
ここで「(退職後に)どうなりたいか?」を考えて得られた答えが強ければ強いほど、引き寄せの法則なのか必要な情報を無意識に取りに行くようになります。
2.必要な生活費を計算する
退職後にどうするかを決めつつ、必要な生活費を計算します。まだ収入があるうちに、収支の可視化をしておきましょう!自分の生活スタイルを見直す良い機会にもなります。
今、自分はいくらで生活しているのか?
また、自分の最低限の生活にはいくら必要なのか?を計算します。
月々の生活費だけでなく、自動車税や月々の任意保険料も視野に入れます。車検とかも忘れずに!
固定費はできるだけ抑えたいところですので、この時に固定費の見直しを行うとより手堅く行けます。

3.生活防衛資金を貯める
退職してから、失業保険を受け取るまでに、7日間の待機期間と2か月の給付制限期間※が発生するので、最低でも2か月分の生活費は必要です。ですが、「しばらくゆっくりしよう」あるいは「独立しよう」と考えている方は失業保険はアテにし過ぎてはなりません。なぜならば、想像以上に退職後の税金がかかるからです。退職するタイミングにもよるとは思いますが、『住民税』と『国民健康保険料』、それから『国民年金保険料』が攻めてきます。
また、注意して欲しいのは毎月の給与から天引きされている『厚生年金保険料』については、退職月に2か月分が持っていかれますので、今月もこれくらいは入ってくるはず…と思っていると、「え゛!いつもよりも給料少ないんだけど!!!」となります。
なので、転職を考えて居ない場合には例えば毎月の生活費が20万円必要だとすると、余裕を持って最低でも100万円くらいの貯蓄があると安心できるかなと思います。税金を支払いつつ、2か月後の失業保険を貰うまでは食いつなげます。
私の場合は、前年度(2023年度)の年収が約550万円で昨年(2024年)9月末付で退職したのですが、住民税が残り2期分(約18万円)と国民健康保険料が4期分(約20万円)、国民年金保険料が6か月分(10.2万円)でした。約50万円が税金として持っていかれることになりました。
※今年(2025年)の4月以降は、給付制限期間が1か月になるようです。また、失業保険の給付日数は雇用保険への加入期間に応じて異なりますので、そこは事前にチェックが必要になります。
5年以内に3回以上自己都合で退職した場合は、給付制限期間が3か月となる点にも注意が必要です。
4.FP3級の知識を入れておく
これはですね、私自身、勉強して本当に良かったなって思う資格でした。日本の社会保障制度(健康保険、雇用保険、年金)とか任意保険、資産運用とか税金の知識が学べることで、退職へ抱く不安が幾分か軽減されました。
特に、私自身、給与から天引きされている社会保険料のことって実は何も知らなかったんですよね。
健康保険料、雇用保険料、厚生保険料、所得税、住民税って…毎月毎月、お賃金から引かれすぎでは!?って常に思ってました。
『3.生活防衛資金を貯める』のところで出てきた言葉が良くわからない、なんて方には絶対オススメしたい知識です。退職後すぐに就職しない場合は健康保険の切り替えや年金の保険区分の変更なども必要になってきますので。
仕組みを知ると、ただただ保険料を支払っているだけでなく、しっかりと恩恵を受ける場面も出て来るし、必要な時にちゃんと必要な制度として保険金を受けることができるようになりますので、やっておいて損はないです。

5.副業を育てるor副業への投資を済ませておく
退職後の自身の「保険」となるよう、収入があるうちに副業へ取り組んでおくと良いです。
あるいは、副業への投資を済ませておくと良いです。
注:値段が高いだけで中身が薄い情報商材などに嵌まってしまわないように気を付けてくださいね!!
私はと言いますと、毎日朝早く出勤しては夜遅く帰宅する、という生活だったこともあり、全然副業らしい副業はやってきませんでした。休日出勤も多く、何も無い本当の貴重な休日はもう全くもって寝て終わる、そんな疲労困憊な生活を送っておりました。
ですが、せめてもの悪あがきにブログを作ってみたり、副業の情報収集をしたりはしておりました。ブログに至っては、今でこそWHAの知識のおかげもあり、そこそこの記事数になり、見栄えも良くなりましたが、当時は良くわからないしで作っただけで放置でしたね…。
そんなわけで、私は会社を辞める前にライティングのスキルだけでも身に着けようと、『フリーランス・ヒーローズ・ギルド』という「令和の虎」でお馴染みのaki社長が作った講座郡の中の、ライティングに関する教材(WHA:ライティング・ヒーローズ・アカデミア)に自己投資しました。
動画一つ一つは短く作られていてサクサク受講できますし、素敵な仲間たちと意見交換をしつつ進めて行けるところが利点です。ただし、コミュニティとして意見交換しながら進めることを前提にしているので、一人で黙々とやりたい方にとっては、痒いところに手が届かずもどかしい教材かもしれません。
結構勇気の要る金額だったので当時は私もかなり悩みましたね…。
配信とかを良く聴いていてaki社長の人柄がわかっていたのもあって、最後はもう「この人とお近づきになるためのコミュニティへの会員権だ!」みたいな感覚で、思い切って行きました。サブスクではなく買い切りだったところも決め手でした。結果として私の場合は正解の選択になっています。切磋琢磨しているコミュニティメンバーを見ているだけでもかなり刺激になりますし、仲間が居ると漠然とした不安はかなり薄れます。
もし興味があれば、アフィリエイトリンクになりますがこちら貼っておきますね。
フリーランスヒーローズ ギルド ー WRITING HEROES ACADEMIA
6.会社の福利厚生のポイントがあれば使っておく
完全に退職することを決めたら、退職日から逆算して余裕を持って使い切っておきましょう。せっかくあるのに使わずに辞めてしまう方も居るとかで、忘れがちなので記載いたしました。
7.就業規則や給与規則などに目を通す
賞与(ボーナス)を貰える条件とか、退職金に関する支給条件とかをしっかり把握しておく必要があります。”賞与支給の何日前まで在籍していること”とかの条件があったり、退職金って実は会社としては支払う義務がないそうで、会社によっては退職金がなかったり、退職金の制度そのものはあるけれども申請しないと支給されない、なんてところもあるとか。
ですので、しっかりと目を通して損しないようにしてくださいね。
まとめ
そんなわけで、私の経験からやっておくと良いことを記載してみました。恐らく、皆さんの置かれている環境によっては全然役に立たないかもしれません。
それにしたって、退職ってかなり勇気が要りますよね。会社員としてずっと働いていて、その期間が長ければ長いほど余計に恐怖です。そんな恐怖から実は私は退職になかなか踏み切れず、結果的に退職したいと思い始めてからうだうだと1年半ほどかかってしまいました。
最後は体調不良により「心が潰れるくらいならば辞めてしまおう!」という思い切りです。
ただ、辞めてみて意外となんとかなっているんです。
時間ができたからか、はたまた、ストレスが減ったからか、それとも、体調が回復してきたからか。
心(いわゆる精神面)にダメージが蓄積すると回復には時間がかかるとは良く言われますが、自覚症状が出ていてなんとかコントロールできていた私でも回復には3か月くらいかかった気がします。
不安が無いと言えば嘘になりますが、じっくりと自分と向き合ったりして、これからの自分がどのような道を歩むのかワクワクしている自分も居るんですよね。
そんなわけで、一度きりの人生ですので少しぐらい休んだって良いと思うのです。
健康を蔑(ないがし)ろにしてはダメですよ!
自分をもっとだいじに。

.webp)








