日本の政治を支える「国会」は、衆議院と参議院という二つの議院で構成されています。どちらも法律をつくる役割を担っているにもかかわらず、なぜ二つの院が必要なのでしょうか。そして、それぞれにはどのような違いがあるのでしょうか。
本記事では、日本が採用している「二院制」のしくみをもとに、衆議院と参議院の制度的な違いや、それぞれに与えられた役割の特徴を丁寧に解説していきます。今回は「政治を動かすしくみの構造」を理解することを目的とした内容になります。
選挙報道や国会中継でよく耳にする言葉の背景にある制度を知ることで、政治のニュースがより立体的に見えてくるはずです。
制度のしくみと、政治の立場──「衆参」と「与野党」はどう違う?
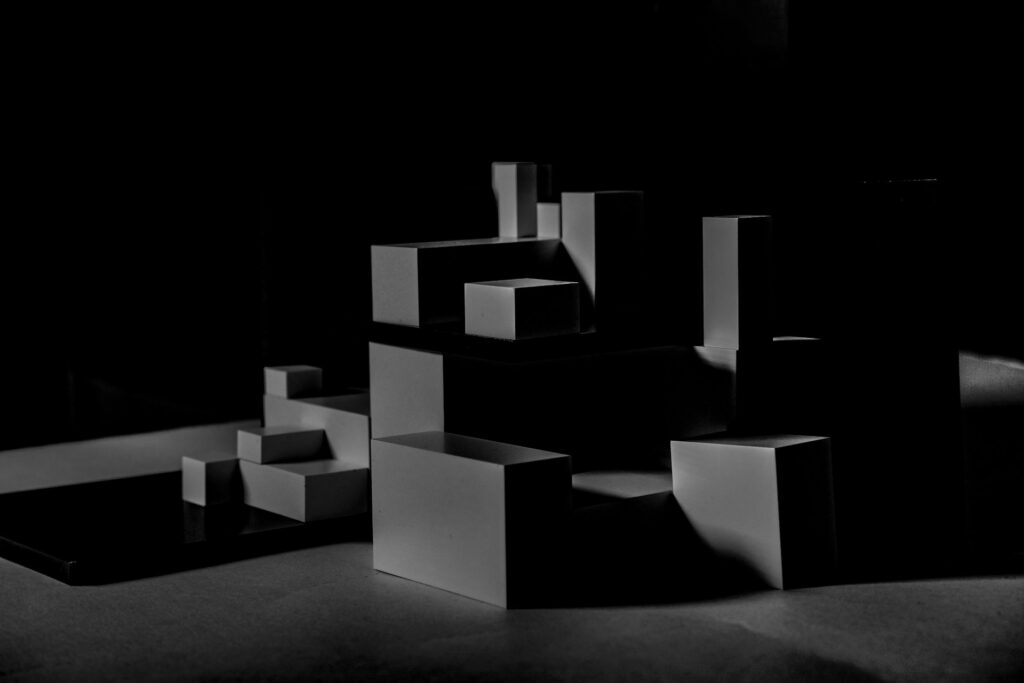
衆議院と参議院の違いを理解するうえで、区別しておきたい大切な視点があります。それが、「制度としてのちがい」と「政治的な立場のちがい」です。衆参与野党なんて言葉も結構耳にしますよね。
この2つは混同されがちですが、それぞれ役割も構造もまったく異なるものです。
衆議院と参議院は、「制度」としての違い
衆議院と参議院は、いずれも日本国憲法に基づいて設けられた制度としての議院です。
国会を構成する対等な機関として、法律の制定や予算の審議など、共通の機能を担っていますが、任期や選挙のしくみなどに制度的な違いがあります。
これが、この記事で主に扱う「制度としての違い」です。
与党と野党は、「政治的な立場」のちがい
一方で、国会には「与党」と「野党」という政治的な立場の違いも存在します。
これは制度ではなく、政党ごとの役割やポジションに基づく分類です。
- 与党:衆議院で多数を占め、内閣を構成している政党(または連立政権)
- 野党:与党に属さず、政府の方針に対して異なる意見や提案を行う政党
与党・野党は、衆議院にも参議院にもそれぞれ存在しており、議論や対立、協調を通じて政治を動かしています。
つまり、「衆議院=与党」「参議院=野党」ではないという点に注意が必要です。
それぞれの軸を意識する
| 区分 | 内容 | どこで決まるか |
|---|---|---|
| 衆議院・参議院 | 制度の構造の違い | 憲法・法律 |
| 与党・野党 | 政治的な立場の違い | 選挙の結果・政党の行動 |
この記事では、こうした構造を踏まえながら、主に「制度としての衆議院と参議院の違い」に焦点を当てて解説していきます。途中で与党・野党という用語が出てきた場合も、それが制度上の違いではなく、政治上の立場の話であるという前提で読み進めてください。

衆議院と参議院は、なぜ二つ存在しているのか

国会には、衆議院と参議院という二つの議院があります。どちらも立法を担う機関ですが、なぜ二つに分かれているのでしょうか。このセクションでは、「二院制」という制度が設けられている背景と、それによって政治にどのような効果が生まれているのかを解説します。
国会は「一つ」、議院は「二つ」
日本国憲法第41条には「国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である」と定められています。そして第42条では、「国会は、衆議院および参議院の両議院でこれを構成する」と規定されています。
つまり、国会は一つですが、それを構成する議決機関として二つの議院(衆議院と参議院)が存在しています。この仕組みを「二院制」と呼びます。
二院制が採用される理由
一院制に比べて、二院制には時間や手間がかかります。それでもあえて二つの議院を置くのは、一つの視点だけで法律や政策を決定してしまうことのリスクを避けるためです。
- 多数派の暴走を防ぐ
- 一方の議院で見落とされた問題点を、もう一方が拾い上げる
- 民意の異なる層をそれぞれが代表する
こうした多角的な視点と、慎重な議論を制度として担保するために、衆議院と参議院は並立して存在しています。
各国に共通する考え方
二院制は日本だけの制度ではありません。アメリカ、ドイツ、イタリア、インドなど、多くの民主主義国家がこの制度を採用しています。
それぞれ制度設計の意図は異なりますが、共通しているのは「立法過程に多様性とブレーキを持たせる」という目的です。複雑な社会において、すべてを一つの議会で決めてしまうよりも、異なる立場の議員が議論を重ねた方が、制度としての信頼性が高まるという考え方です。
衆議院と参議院は、形式上は同じ「国会の構成要素」ですが、その制度には大きな違いがあります。
次のセクションでは、それぞれの構造や選び方、任期などの具体的な違いを見ていきます。
衆議院と参議院の制度的な違いを整理する

衆議院と参議院は、どちらも国会を構成する議院であり、法律の審議や予算の議決などを行っています。形式上は対等ですが、その制度設計には明確な違いがあります。
このセクションでは、両院の「任期」「解散制度」「選挙のしくみ」「立候補の条件」など、構造上の違いを整理していきます。
任期とは何か──議員の活動期間の定め
国会議員には、それぞれ「任期」が定められています。任期とは、選挙によって選ばれてから次の選挙までの活動期間のことを指します。国会は「常に開かれているわけではない」のではなく、議員の任期が満了すれば、新たに選挙が行われて議席が入れ替わることになります。
ただし、衆議院と参議院では、その任期の長さや途中の扱いに違いがあります。
衆議院と参議院の任期の違い
- 衆議院:任期は「4年」。ただし、任期満了前に「解散」が行われることがある。
- 参議院:任期は「6年」。解散はなく、3年ごとに半数が改選される。
ここで注意が必要なのが、「解散」という制度です。
解散とは何か──衆議院にだけ認められた制度
衆議院には「解散」という制度があります。これは、任期を全うする前に衆議院をいったん“白紙に戻す”制度で、これによって全議員の職が一時的に失われ、総選挙で新しい衆議院議員を選び直すことになります。
この解散を行うかどうかを決定するのは、内閣(正確には首相)です。
憲法第7条に基づき、首相の助言と承認により天皇が解散を形式的に宣言します。
つまり、
- 解散されるのは衆議院(=議員たち)であり、
- 内閣が“解散を決定する側”という構図です。
なお、内閣自身が「解散」されることはありません。内閣が退陣する場合は「総辞職」という手続きが別に用意されています。
一方、参議院にはこのような制度はなく、6年の任期を全うすることが前提です。3年ごとに全体の半数を選び直す「半数改選制」により、一度に全議員が入れ替わることはありません。そのため、政治的な流れに左右されにくく、長期的な視点で議論を積み重ねやすいという特徴があります。
選挙制度と定数の違い
衆議院も参議院も、どちらも国民による選挙で議員が選ばれますが、選び方のしくみ(=選挙制度)には大きな違いがあります。
衆議院の選び方
衆議院の選挙は、「小選挙区比例代表並立制」という方式が使われています。
これは、有権者が「候補者(個人)」と「政党」の2つに投票する制度で、2つの選び方が並行して行われるのが特徴です。
- 小選挙区制(289人):全国を細かく289の選挙区に分け、それぞれの区で1人だけ当選する方式です。
→ 地元の代表として、顔が見える候補者を選びやすいのが特徴です。 - 比例代表制(176人):全国を11のブロックに分け、政党への投票数に応じて議席を割り当てる仕組みです。
→ 各政党があらかじめ届け出た名簿から、得票数に応じて候補者が当選します。
このように、衆議院では「地域代表」と「政党支持」両方の視点から政治に参加できる仕組みが採用されています。
参議院の選び方
参議院でも、選挙区制と比例代表制が併用されていますが、制度の設計が異なります。
- 選挙区制(74人):都道府県ごとに定められた選挙区から、地域の有権者によって複数の議員を選ぶ方式です。
→ 1人区・2人区のように、定数は都道府県によって異なります。 - 比例代表制(50人):全国を1つの選挙区とみなし、全国単位で政党に投票します。
→ この比例代表では、政党の名簿だけでなく「個人名」でも投票できる非拘束名簿式が採用されています。
有権者が支持する候補者を名指しで応援できるしくみです。
このように、衆議院は政権選択を強く意識した制度、参議院は多様な意見を反映させやすい構造となっており、
それぞれの院に求められる役割に応じて、選挙制度も工夫されています。

被選挙権年齢と立候補条件の違い
立候補できる年齢にも差があります。
- 衆議院議員:25歳以上
- 参議院議員:30歳以上
参議院のほうが高年齢を条件としているのは、より成熟した判断力や見識が求められるという制度的背景があるためです。これは、参議院が「良識の府」と呼ばれ、安定した視点で政策を見直す機関と位置づけられていることとも関係しています。
このように、任期・解散の有無・選挙の制度・被選挙権の条件など、両院には明確な制度上の違いがあります。
次のセクションでは、こうした違いが「権限の差」につながっている点──特に衆議院にだけ認められている強力な機能について見ていきます。
衆議院にだけ認められた強い権限とは

衆議院と参議院は、どちらも国会として対等な立場にあるとされています。しかし、すべての面で権限が等しいわけではありません。実際には、衆議院にのみ認められた“強い権限”がいくつか存在しています。
このセクションでは、その主な権限と背景を制度的に整理し、なぜ衆議院が優越的な機能を担っているのかを見ていきます。
衆議院の優越が認められる場面
日本国憲法には、特定の案件について「衆議院の議決が優先される」ことを明記した条文があります。主に以下の3つの場面で、衆議院に優越が認められています。
予算の先議権(憲法第60条)
国家予算の審議においては、必ず衆議院から先に審議が始まると定められています。
予算は国の行政の出発点であり、速やかな執行が求められるため、選挙によってより直接的に国民の声を反映する衆議院に先議の権限が与えられています。
条約の承認(憲法第61条)
外交上の条約も、衆議院の優先審議が認められています。国際関係は迅速な対応が必要とされる場面が多いため、機動性のある衆議院が主導する形が取られています。
法律案の再議決(憲法第59条)
最も象徴的な優越は、法律案における再議決の権限です。
衆議院で可決された法案が参議院で否決された場合、衆議院が三分の二以上の賛成で再可決すれば、その法案は成立します。
これは、参議院が「見直しの場」であることを前提にしつつも、最終的にはより民意に近い衆議院の意思が尊重されるという制度設計です。
内閣不信任決議権──政権の命運を握る機能
さらに大きな違いとして、内閣に対して不信任決議を出せるのは衆議院だけという点が挙げられます(憲法第69条)。
この不信任決議が可決されると、内閣は以下のいずれかを選ばなければなりません。
- 10日以内に衆議院を解散する
- または、自ら総辞職する
つまり、政権そのものの継続可否を左右できるのは衆議院のみであり、ここに政権との直結性という大きな役割の差があります。
なぜ衆議院にだけ強い権限があるのか
これらの優越規定は、単なる序列を意図したものではありません。以下のように、制度上の理由は明確です。
- 衆議院は任期が短く、解散もあるため、常に最新の民意が反映されやすい
- 選挙制度上、政権選択が前面に出る構造となっており、政府との連動性が高い
- そのぶん、政治的責任もより重く問われる立場にある
一方で、参議院には解散がなく、継続的な視点で冷静な審議を行えるという利点があります。そのため、参議院の役割は「慎重な再検討」に置かれ、衆議院のスピードに対するブレーキ機能を果たすように設計されています。
このように衆議院は「政治の推進力」を持つ存在として、制度的にも強い権限が与えられています。
では、参議院にはどのような意味と役割が託されているのか──次のセクションでは、参議院が果たす「再考と抑制」の機能に注目します。
参議院が果たす「再考と抑制」の役割

衆議院が政治の推進力であるなら、参議院はそのスピードに対する抑制力です。法律の成立において、二つの院が同じ内容を二度審議するのは、ただの形式的な重複ではありません。
このセクションでは、参議院に託されている「再検討」や「冷静な視点」といった役割に焦点を当て、その意義を制度的に整理します。
参議院は「再考の場」として設計されている
参議院は、憲法上も衆議院と同様に立法権を持つ独立した議院ですが、制度上の特徴(解散がない、任期が長い、半数改選など)から、より持続的・安定的な議論に向いた構造となっています。
衆議院で可決された法案が、参議院で再度審議されることで、以下のような再評価が可能になります。
- 一時的な世論や政局に流されていないか
- 条文や制度設計に抜けがないか
- 実務的・専門的観点から問題がないか
これにより、立法の質を確保し、拙速な決定を防ぐ役割を果たしています。
「良識の府」としての期待
参議院はしばしば「良識の府」と表現されます。これは、以下のような制度設計に裏打ちされたものです。
- 任期が6年と長く、政治的変動に左右されにくい
- 解散がないため、急激な民意変化に巻き込まれにくい
- 被選挙権が30歳以上とされ、より経験や見識が期待されている
こうした背景から、参議院にはより中立的かつ専門性の高い判断が求められており、感情論や短期的判断を超えた“修正力”が制度的に期待されているのです。
審議を重ねることで見えてくるもの
参議院での再審議は、単に「確認」のためではありません。
委員会での質疑や、専門家からの意見聴取、附帯決議などを通じて、衆議院では十分に取り上げられなかった論点が浮かび上がることもあります。
とくに次のようなケースでは、参議院の役割が大きく機能します。
- 与党が衆議院で多数を占めている場合
- 衆議院が解散を経て新しい体制になった直後
- 対象となる法案が制度的に複雑で、専門的知識を要するとき
参議院での慎重な議論によって、法案の内容が修正されたり、見直しの契機となったりすることもあり、これがまさに「再考と抑制」の力といえます。
参議院は、衆議院とは異なる時間軸と構造を持つことで、国会全体のバランスを保つ役割を担っています。
次のセクションでは、こうした制度の“利点”と“限界”の両面を整理し、二院制という仕組みの全体像を見つめ直していきます。
二院制のメリットと課題

衆議院と参議院が並立する「二院制」は、日本の政治制度における特徴のひとつです。ここまでのセクションで見てきたように、両院には役割や構造に違いがあり、それぞれの存在には理由があります。
このセクションでは、二院制がもたらす主なメリットと、あわせて議論の対象となっている課題について整理します。
メリット①:多角的な視点による慎重な審議
最大の利点は、法案を二つの異なる視点から審議できることです。
衆議院ではスピーディに政策が進む一方、参議院では冷静な検証が可能となり、拙速な判断や思いつきの立法が抑制されます。
- 衆議院:民意の動きに敏感に反応しやすい
- 参議院:長期的・専門的な検討に向いている
このバランスがあることで、立法の質を高めることができるというのが二院制の本質的な価値です。
メリット②:民意の多層的な反映
選挙制度の違いや任期のズレによって、衆参の構成が異なる場合があります。
このような“民意のズレ”は否定的に捉えられがちですが、見方を変えれば、同時点における多様な意見を反映できる仕組みとも言えます。
- 衆議院:一時的な世論や政権評価が強く反映される
- 参議院:継続性を重視した視点が保たれやすい
複数の選挙軸が併存することで、政治が一つの方向に偏りすぎるのを防ぐ効果があります。
課題①:「ねじれ国会」の発生
一方で、衆議院と参議院の多数派が異なると、いわゆる「ねじれ国会」となります。
この状態では、法律案や予算案が一方の院で可決されても、もう一方で否決されるなど、国会の意思決定が停滞することがあります。
とくに予算や重要法案の審議において、調整に時間がかかり、政治全体の動きが鈍る原因にもなります。
課題②:立法手続きの複雑化と重複感
すべての法案が衆議院と参議院の両方で審議されるため、時間・労力・手続きが二重にかかるという指摘もあります。
とくに政治的対立が強い時期には、「形式的な否決と再可決の応酬」が繰り返され、建設的な議論が見えにくくなることもあります。
課題③:「参議院不要論」の存在
こうした背景から、時折「参議院は必要なのか?」という声も上がります。
とくに衆議院が法案を再可決できる権限を持っていることや、政権を決める力がないことから、「参議院の実効性が見えにくい」とする批判もあります。
ただし、これは「制度上の機能」と「政治的な運用」の問題が混同されているケースも多く、参議院の存在意義は制度的には明確に位置づけられています。
二院制には、拡張的で多層的な民主主義を支える力がある一方で、制度の複雑さや政治的な停滞を招く側面もあります。
次のセクションでは、これまでの整理をふまえて、衆議院と参議院の存在が日本の民主主義にとってどのような意味を持つのかを改めて考えてみます。
まとめ|一つの国会に二つの議院がある意味を捉え直す
衆議院と参議院。二つの議院を通じて成り立つ日本の国会は、単なる制度上の形式ではなく、政治のバランスと深みを生むために設計されたしくみです。
ここまで見てきたように、それぞれには違いがあり、役割があり、そして共存することに意味があります。
衆議院は、民意の推進力
任期が短く、解散もあり、政権の行方を左右する衆議院は、政治のスピード感や変化への対応力を担う存在です。
内閣の信任に直結し、予算・条約・法律の再可決といった強い権限を持つのも、その“即応性”が求められているからです。
参議院は、慎重なブレーキと再考の場
対して参議院は、選挙制度や任期の設計により、より安定した長期的な視点を保ちやすく、「良識の府」としての役割を果たしています。
政局や一時的な世論に左右されすぎず、法案の質や制度の持続性を冷静に見直す役割が託されています。
対立ではなく、補完し合う仕組み
両院は、どちらかが正しいという関係ではなく、一つの法案に対して異なる立場から見直す“視差”のような存在です。
政治の現場では時に「ねじれ」や「停滞」の原因とされることもありますが、民主主義の健全性を支える“抑制と均衡”として見ることができます。
選挙のたびに注目される「与党」「野党」の議席構成も、この二つの議院のなかで組み合わさり、政権や政策の方向性を決めていきます。
制度としての衆議院・参議院の違いを知ることは、政治報道や法案審議を“構造の目”で捉える力につながります。
今の政治を表面的な対立としてではなく、「どういう仕組みで支えられているのか」を理解する。
それは、私たち一人ひとりが政治と関わっていくうえで、揺るがない土台となってくれるはずです。

より、詳しく知りたい方は、一般向けの入門書を一冊通して読むという方法もあります。
【PR】今さら聞けない! 政治のキホンが2時間で全部頭に入る
↑↑Amazonのサイトへ飛びます
※本書は、多くのレビューで「政治の全体像を把握しやすい入門書」と評価されているものです。
※筆者自身が内容を精査したものではないため、参考資料の一例としてご紹介しています。
よくある質問
衆議院と参議院って、そもそもどちらが“偉い”んですか?
制度上、どちらが上位ということはありません。
衆議院・参議院はどちらも憲法に定められた「国会の構成要素」であり、立法機関としては対等な位置づけです。
ただし、衆議院には予算の先議権、条約の優先審議、法案の再可決、内閣不信任決議といった一部の分野で優越が認められている権限があります。これは、「より民意に近く、迅速な対応が求められる院」として設計されているからです。
「ねじれ国会」ってなぜ問題視されるんですか?
「ねじれ国会」とは、衆議院と参議院で多数派の政党が異なる状態を指します。
この状態になると、法案や予算案が一方の院で可決されても、もう一方で否決されて進まない、という事態が起こりやすくなります。
本来は多様な意見を反映できるという利点もありますが、与野党の対立が強いと、政治の停滞や調整の長期化が問題になることもあります。
衆議院が「解散」されるのはなぜ?参議院ではなぜ解散がないのですか?
衆議院の「解散」とは、任期を途中で打ち切り、議員をいったん全員退任させて選挙をやり直す制度のことです。
これは政権に行き詰まりが生じたときなどに、国民に再び信を問うための手段として設けられています。
一方で参議院には解散がありません。参議院は「良識の府」として、政治の安定性や継続性を担保する役割を持っており、3年ごとの半数改選という仕組みで議会の一貫性を保つ構造になっています。
解散後に再び議員になった場合、元の残っている期間の任期が採用されるのですか?
いいえ。
たとえば任期4年の衆議院議員が、2年後に解散があって再び選挙で当選した場合でも、そこから新たに4年の任期がスタートします。
つまり、解散によって前の任期は終了するというのが制度の考え方です。
衆議院と参議院があるうえに、与党と野党まであるのは、どういうことなんですか?
日本の政治には、しくみとしての“衆議院と参議院”と、立場としての“与党と野党”があります。
衆議院と参議院は、どちらも国会を構成する“制度”としての役割を持っていて、法律や予算などを話し合う場所です。
一方で、そこに所属する政党には、「今の内閣を支える側(=与党)」と「それ以外の側(=野党)」という“立場”の違いがあります。
つまり、「衆議院と参議院」は“場所・しくみ”のちがいであり、「与党と野党」は“考え方・役割”のちがいです。
それぞれが組み合わさって、政治が成り立っています。
衆議院と参議院には、それぞれ与党と野党がどう関わっているんですか?
与党と野党は、衆議院にも参議院にもそれぞれ存在します。
ただし、どの政党が“与党”とされるかは、衆議院の議席数で決まります。
衆議院で多数の議席を持つ政党(または連立グループ)が政権を担い、内閣を構成します。これが「与党」です。
一方、参議院にも同じ政党の議員はいますが、そこでの議席数によっては“野党が多数派”になることもあります。
このように、衆議院で与党が多数でも、参議院では野党が優勢になることがある──これが「ねじれ国会」と呼ばれる状態です。参議院ではその場合、政府の政策を見直したり、修正を求めたりする役割が強まることになります。
小選挙区比例代表並立制って、どんな仕組みですか?
衆議院の選挙では、「小選挙区制」と「比例代表制」の両方を組み合わせた制度が使われています。これを「小選挙区比例代表並立制」と呼びます。
- 小選挙区制:
全国を289の地域(=選挙区)に分け、それぞれの区で1人だけを選ぶ仕組みです。
→ 地域ごとに顔の見える候補者を選べるのが特徴です。 - 比例代表制:
全国を11のブロックに分けて、政党に投票し、得票数に応じて議席を分配する仕組みです。
→ 地域よりも政党の政策や全体方針を重視して投票できます。
有権者は投票所で、「小選挙区の候補者(個人)」と「比例代表の政党」の2つに票を入れます。
こうして、一人ひとりが“個人を選ぶ目”と“政党を選ぶ目”の両方で政治に関わることができる制度です。
選挙区ってなんですか?どうやって分けられているんですか?
選挙区とは、選挙を行う際に地域ごとに区切られた“投票エリア”のことです。
たとえば、衆議院の小選挙区では、日本全国が289の選挙区に分かれており、各区から1人だけ国会議員を選びます。
これは市区町村の境界に基づいており、人口のバランスを見ながら調整されています。
また、参議院の「選挙区制」では、都道府県ごとに選挙区が設定されていて、都道府県単位で複数人の候補者を選ぶ仕組み(中選挙区制に近い)になっています。
つまり、
| 議院 | 選挙区の単位 | 選び方 |
|---|---|---|
| 衆議院(小選挙区) | 細かく分けられた地域(市区町村単位) | 1人だけ選ぶ(小選挙区制) |
| 参議院(選挙区) | 都道府県ごと | 複数人を選ぶ(定数は地域による) |
選挙区は、「どの地域の代表を誰に託すか」を考える仕組みであり、地元と政治をつなぐ大切な回路でもあります。
その他にも、「選挙の方法」や「政党の構成」など、気になる点があればぜひ調べてみてください。
制度のしくみと立場のちがいが見えてくると、政治のニュースもぐっと理解しやすくなります。
.webp)

