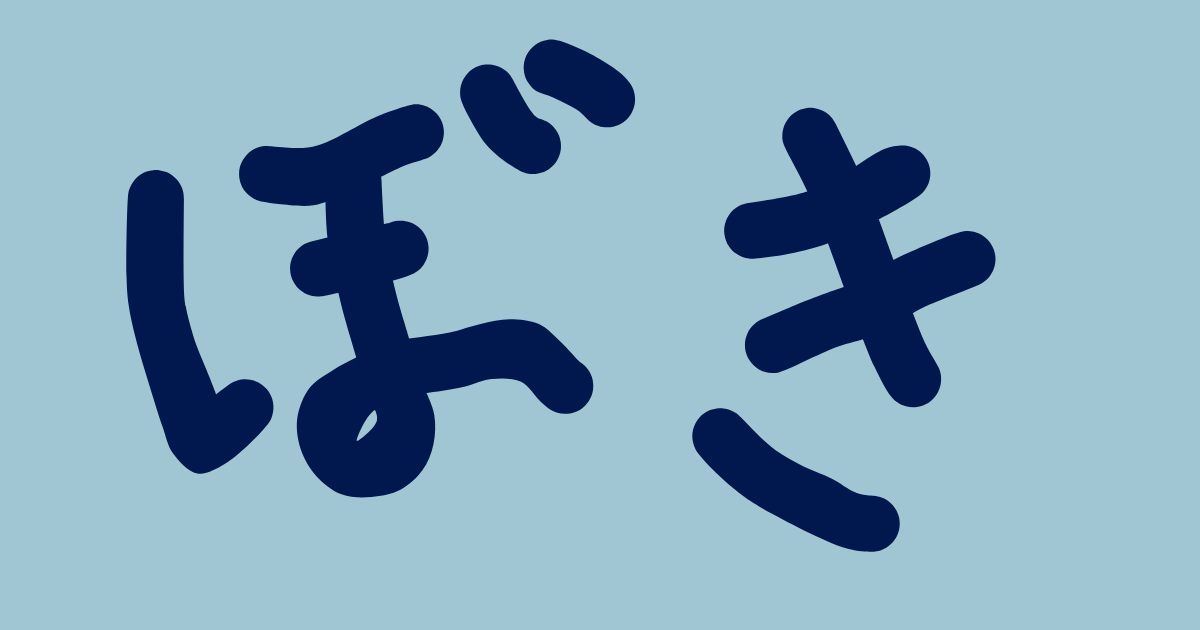簿記3級を簡単だと言った人、誰ですか!!!
簿記2級までなら誰でも取れるって言った人、誰ですか!!!
めっちゃ難しいじゃないですか!!!
簿記3級もなかなかに苦戦したけれども、2級はもっと苦戦中。
そんなわけで、ワタクシのお悩みをAIに聞いてもらったところ、割と参考になりそうな内容もあったので書いて行きますね。簿記取得を目指して頑張っているみなさま、一緒に頑張りましょ!
アウトプットのコツ
 みくまり
みくまり勉強の際に、アウトプットがどうしてもやりたくない時ってどうしたら良いですか?
アウトプットがどうしてもやりたくないと感じるのはよくあることです。特に簿記のように問題演習や仕訳の練習が重要な科目では、アウトプットへの抵抗感は成績にも直結しやすいです。以下は、アウトプットへの抵抗感を減らし、少しでもやりやすくするための方法です。
小さなアウトプットから始める
いきなり模擬試験や大量の問題を解こうとするとハードルが高いです。
おすすめ:
- 1問だけ解いてみる。
- 仕訳1つだけ書いてみる。
- 5分だけタイマーをかけて取り組む。
短時間でも手を動かすことで、脳が「できるかも」と感じやすくなります。
インプットとセットで考える
アウトプットだけだと辛い場合、インプットを先にして「これは使える!」と感じた知識をすぐに試す形でアウトプットしましょう。
具体例:
- 新しい仕訳パターンを学んだら、その場で似た問題を1問だけ解く。
- 理論を読んだら、簡単な穴埋め問題を解いてみる。
ご褒美を設定する
アウトプットをした後に、好きな飲み物や休憩を用意しておくと「やったらいいことがある」と脳が認識します。
例:
- 問題を3問解いたらコーヒーを飲む。
- 30分だけスマホタイムを許可する。
アウトプットの目的を再確認する
「なんのためにアウトプットをするのか」を明確にすると、やりやすくなります。簿記の場合、合格のために「理解度の確認」と「ミスの傾向を掴む」ためですよね。目的を意識すると、少し取り組む気持ちが変わります。
書くより話すアウトプットに変えてみる
書くのが面倒なときは、仕訳の解説や理論を「声に出して説明」してみてください。音読や独り言でもアウトプット効果があります。
例:
- 「これは借方に現金、貸方に売上を立てるんだな」とつぶやく。
- 問題文を読みながら「ここは費用だから…」と解説してみる。
アウトプットの方法を変える
同じ形式ばかりだと飽きやすいので、たまには別の方法を試しましょう。
代替案:
- フラッシュカードを使う。
- 穴埋め形式で記述する。
- 頭の中で解いて、解答を確認するだけにする。
まとめ
アウトプットが嫌なときは、「小さく始める」「ご褒美」「目的の再確認」などでハードルを下げてみましょう。少しでも手を動かせば、続けやすくなるはずです。まずはできそうなものから試してみてください!
やる気のムラの対策
 みくまり
みくまりなんの苦も無く問題に熱中できる時と、問題文1行目を読もうとするだけで拒絶が出てしまう時があるのですが、この差ってなんだと思いますか?
同じ問題でも「熱中できるとき」と「1行目から拒絶してしまうとき」があるのは、いくつかの要因が絡んでいます。特に考えられる原因は以下の5つです。
ドーパミンの分泌量の差
問題に熱中できるときは、脳内でドーパミンが分泌されている可能性が高いです。ドーパミンは「報酬予測」に関係していて、
- これが解けたら面白い!
- できたら嬉しい!
といった感覚を生みます。
拒絶感が出るときは?
- ドーパミンが不足している。
- 報酬が見えにくい(解けても達成感が薄い)。
対策:
- 小さな報酬を設定:1問解けたら好きな飲み物を飲む。
- 簡単な問題で勢いをつける:最初は絶対解ける問題から。
エゴの消耗(意志力の低下)
意志力は有限で、疲れていたりストレスが溜まっていると、意志力が枯渇 して「やる気」が出にくくなります。これを「エゴの消耗(Ego Depletion)」と呼びます。
- 熱中できるとき:意志力が十分に残っている。
- 拒絶感が出るとき:意志力が枯渇している。
対策:
- 短時間の休憩:5分だけ深呼吸やストレッチ。
- エネルギー補給:少し甘いものやナッツを食べる。
- 最初は眺めるだけ:問題を解かずに読むだけにする。
「期待」と「不安」のバランス
- 期待感が強い:解けそう!面白そう! → 熱中
- 不安感が強い:難しそう…解けないかも… → 拒絶
対策:
- 分解して解く:問題を細かく分けて、「これならできる!」と思う部分から手を付ける。
- 部分点狙い:全問解こうとせず、部分的にできればOKと考える。
- 成功体験:過去に解けた類似問題を振り返る。
自己評価と完璧主義の影響
完璧主義が強いと、「解けなかったらどうしよう」というプレッシャーで拒絶反応が出やすいです。
- 熱中できるとき:結果よりも過程を楽しんでいる。
- 拒絶感が出るとき:「失敗したくない」「解けなかったら意味がない」と考えている。
対策:
- 「失敗OK」のルール:解けなくても次に解ければOKと考える。
- 過程にフォーカス:解答の正しさよりも「どこまで考えたか」を重視。
脳の「切り替えスイッチ」が機能していない
脳は デフォルトモードネットワーク (DMN) と タスクポジティブネットワーク (TPN) という2つのモードを持っていて、
- DMN:ぼんやりしているとき。
- TPN:問題を解くなど集中しているとき。
拒絶感があるときは、DMNからTPNへの切り替えがうまくいっていない可能性があります。
対策:
- 簡単な計算や書き写し:まずは手を動かしてTPNに切り替える。
- 環境の変化:カフェや図書館に移動して刺激を与える。
- タイマー勉強:5分だけ集中と決めてタイマーを使う。
まとめ
- 熱中できるとき:ドーパミンが出ている、意志力が残っている、期待感がある。
- 拒絶感が出るとき:ドーパミン不足、意志力の枯渇、不安や完璧主義。
まずは、小さな報酬を設定したり、簡単な問題で勢いをつけてみてください。やる気の波をコントロールする鍵になります!
活字嫌いのための工夫
 みくまり
みくまり活字が苦手過ぎて、問題文などを読むのが辛いのですが、なんか良い方法ありませんか?
活字が苦手で問題文を読むのが辛いと感じるのは、結構よくあることです。特に簿記の問題文は長くて固いので、余計に抵抗感が強くなりがちです。ここでは、活字が苦手な人でも問題文を楽に読める工夫を紹介します。
音読で「視覚」と「聴覚」を使う
黙読だと活字が頭に入らないときは、音読 が効果的です。
やり方:
- 問題文を ゆっくり声に出して読む。
- 「ここは大事!」と思ったところは 強調して読む。
- 簡単な箇所はサッと流してOK。
メリット:
- 目だけでなく耳も使うので、理解しやすい。
- 読むスピードが一定になるので、詰まりにくい。
「指読法」で集中力を維持
活字が苦手な人は、目だけで追うと集中力が続かないことが多いです。
やり方:
- 指やペンで 行をなぞりながら読む。
- 行を飛ばしたり、戻ったりしない。
メリット:
- 視線が安定して、読み飛ばしが減る。
- 手を動かすことで、集中力が保たれる。
問題文を「分解」して読む
長い問題文は、一度に読もうとすると圧倒されます。
やり方:
- 1文ずつ区切って読む。
- 重要そうな部分は、ペンで線を引く。
- 「前提条件」「聞かれていること」「数字」に分けて読む。
例:
- 【前提】売上高は100万円です。
- 【条件】掛け取引で月末締めです。
- 【質問】どの勘定科目を使うべきか?
メリット:
- 一度に読む情報が減り、頭に入りやすい。
- 必要な箇所だけに集中できる。
「読み上げアプリ」を使う
スマホやPCの読み上げ機能で、耳で聞く勉強 もおすすめです。
おすすめアプリ:
- Googleの読み上げ機能(Android)
- VoiceOver(iPhone, iPad)
- PCの読み上げソフト(Windows: ナレーター, Mac: VoiceOver)
やり方:
- 問題文をコピペして、読み上げてもらう。
- 再生速度を調整して聞きやすくする。
メリット:
- 活字が苦手でも耳ならスムーズに理解できる。
- 聞きながらメモを取ることで、記憶に残りやすい。
マーカーを使った「色分け読み」
重要な箇所だけピックアップして読む方法です。
やり方:
- 数字は「青」、条件は「赤」、結論は「緑」など色分け。
- 色を見ながら、重要な部分だけ先に読む。
メリット:
- どこが大事かが視覚的にわかる。
- すべて読まなくても、重要ポイントを理解できる。
「図解」や「マインドマップ」に変換
文字だけだと辛いなら、図や表 にしてしまう方法です。
やり方:
- 問題文の内容を 図解化(T字勘定やフローチャート) する。
- マインドマップで「条件」「目的」「解答の流れ」を整理。
メリット:
- 視覚情報になると理解しやすい。
- 問題文の全体像がつかめる。
「要約→詳細」の順で読む
最初に細かいところから読むと挫折しやすいです。
やり方:
- まずは問題文の 最後の質問部分だけ 読む。
- 次に、前提条件や数字の部分を読んでいく。
メリット:
- 「何を聞かれているか」がわかってから読むので、理解しやすい。
- 最後の質問だけなら短くて読みやすい。
まとめ
活字が苦手でも、音読、指読法、読み上げアプリ、色分け、図解 などを使えば問題文がスムーズに読めます。まずは、「音読」や「指読法」から試してみるのがおすすめです。少しでも抵抗感が減れば、勉強の効率も上がるはずです!
個人的には「指読法」が割と良い感じでした。
わかる気がするのに頭に入っていく感覚がない
 みくまり
みくまり意味はわかる気がするのに頭に入ってる気がしない現象って何ですか?
「意味はわかる気がするのに、頭に入っている気がしない」という現象は、いくつかの心理学的・認知科学的な概念で説明できます。特に関連が深いのは以下の4つです。
流暢性の錯覚(Illusion of Fluency)
どういう現象?
- 読んだり聞いたりしたときに、「理解できた」と感じるけれど、実際には 記憶に定着していない 状態。
- 簡単に読めたり、スムーズに理解できた気がするときに起こりやすい。
なぜ起こる?
- すらすら読めると、脳が「理解できた」と錯覚するが、 深い理解や記憶の定着は別問題。
- 特に活字を読み流すときや、動画や音声を聞き流しているときに発生しやすい。
対策
- アウトプット:読んだ内容を自分の言葉で説明する。
- 手を動かす:メモを取ったり、要点を書き出す。
- 小テスト:読んだ直後に問題を解く。
動画で講義を聞いている時なんかまさしくこれに陥りますよね!
セマンティック飽和(Semantic Satiation)
どういう現象?
- 同じ単語やフレーズを繰り返し見たり聞いたりすると、その意味がぼんやりして 実感がなくなる こと。
- 例えば、「売掛金」「売掛金」と何度も見ると、意味はわかるのに頭に入っていない感覚。
なぜ起こる?
- 脳が 同じ刺激に慣れてしまい、注意や新鮮さが失われるから。
- 専門用語やよく出る単語ほど起こりやすい。
対策
- 別の言い方で学ぶ:「売掛金」を「後で払ってもらうお金」と置き換える。
- 例文を増やす:用語を含む具体的な例文を作ってみる。
- 少し時間を置く:飽和を感じたら10分ほど別のことをする。
理解と記憶の乖離(Comprehension-Memory Gap)
どういう現象?
- 読んでいるときは理解できているのに、 読み終わった瞬間に内容が曖昧になる こと。
- 読解中は短期記憶に情報が入っているが、長期記憶に移されていないため。
なぜ起こる?
- 短期記憶はすぐに忘れやすく、理解した気になるだけ。
- 長期記憶に定着させるための 復習や反復 が不足している。
対策
- インターバル復習:10分後、1時間後、翌日と復習する。
- 自分の言葉で書く:読んだ内容を簡単にまとめて書く。
- 質問を作る:自分で問題を作って答える。
メタ認知の欠如(Lack of Metacognition)
どういう現象?
- 「理解できたか」を判断する力(メタ認知)が弱いと、 実際の理解度と自分の感覚に差が出る。
- 「わかる気がする」はメタ認知が不十分で、実際にはわかっていない場合が多い。
なぜ起こる?
- メタ認知はトレーニングで強化できるが、普段から意識していないと未発達なまま。
- やりっぱなしで終わらせると、メタ認知が育ちにくい。
対策
- 振り返り:今日学んだことで「わかったこと」「わからないこと」を書き出す。
- チェックリスト:理解したかどうかを確認する質問を用意する。
- 他人に説明:説明できるかどうかでメタ認知を鍛える。
まとめ
- 流暢性の錯覚:スラスラ理解できた気がするだけ。
- セマンティック飽和:同じ言葉で意味がぼやける。
- 理解と記憶の乖離:短期記憶から長期記憶への移行不足。
- メタ認知の欠如:実際の理解度と感覚の差。
まずは、音読や手書きで「流暢性の錯覚」を防ぎ、メタ認知チェック(例: 自分に説明してみる)を試してみると効果的です!
さいごに
こんな感じでAIに壁打ちをしているのですが、結局のところ1問ずつでも良いからちょっとずつ根気強く復習して、アウトプット(問題を解く回数)を増やすことが簿記学習においては一番の近道なのかもしれませんね。
くじけずにファイトです!!!
.webp)