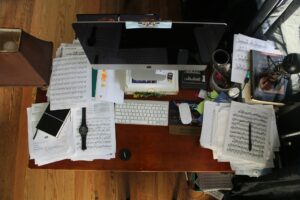今年は、”参院選”こと参議院議員選挙が行われます。
とは言っても、「参院選とは何か」「なぜ行われるのか」がわからないまま、選挙から距離を置いている人は少なくありません。選挙なんてただただうるさいだけで、「なんかやっているな」という印象の方も多いかもしれません。
社会保障や税金、教育、労働環境といった制度の多くは、国会での審議を通して決まっていきます。
日々の暮らしに関わるこうした制度を話し合い、形にしていく場に、私たちは直接関わることはできません。だからこそ、代わりに話し合いに参加する人を決めるための「選挙」があります。
参議院選挙は、その国会の一部を担う議員を新しく選び直す、大切な機会です。
現在の日本の政治に対しては、「声が届かない」「何も変わらない」といった不満や諦めの声が積み重なっています。だからこそ、選挙に行っても何も変わらないという気持ちが強いのも事実。
しくみが見えづらく、声が届きにくいと感じる今だからこそ、なぜ選挙で選ぶ必要があるのかを、あらためて考えることが大切です。
この記事では、参議院議員選挙こと”参院選”の制度や役割を正確に整理したうえで、選挙に参加することが私たちの暮らしにどう関わるのかを、基礎から丁寧に解説していきます。
「選挙」ってそもそも何?──その種類と今回の選挙の位置づけ

「選挙に行きましょう」と言われても、何を決める場なのかがはっきりしないままでは、参加しようという気持ちにはなりづらいものです。まずは、そもそも「選挙とは何か」という基本から整理し、今回の参議院選挙がどこに位置づけられるものなのかを明確にしておきます。
制度を動かす人を決める──それが選挙の役割
選挙とは、社会のルールや制度をどうするかを話し合い、決めていくために、私たちの代表となる人を選ぶ手続きです。
税金の使い道、制度のあり方、社会保障の内容など、暮らしに関わる大きな決定は、私たち一人ひとりでは直接行えません。そのため、私たちは代表となる人を選び、その人たちが議会で議論や決定を行う、というしくみになっています。
つまり、選挙は「制度や仕組みをどう作るかを、誰に託すかを決める場」だといえます。
選挙には大きく分けて2つある
日本では、選挙は大きく次の2つに分けられます。
- 国政選挙: 国の方針や法律を決める人(国会議員)を選ぶ選挙
- 地方選挙: 市町村や都道府県の首長(市町村長・知事)や議員(地方議会議員)を選ぶ選挙
どちらも私たちの暮らしに直結する制度をつくる場ですが、今回行われるのは前者、国政選挙です。
国政選挙には2種類ある
国政選挙の中でも、さらに2つに分かれます。
- 衆議院議員を選ぶ選挙(衆議院議員選挙) → 一般的に衆議院選挙または略して衆院選
- 参議院議員を選ぶ選挙(参議院議員選挙) → 一般的に参議院選挙または略して参院選
この2つの議院が集まって「国会」を構成しており、法律や予算を決める中枢機関として機能しています。

今回の選挙は「参議院議員を選ぶ選挙」
今回行われるのは、「参議院議員」を選ぶための選挙です。
国会のなかで、参議院は安定した議論と制度の検討を担う役割を持ち、6年という長い任期を通じて政策決定に関与します。
参議院選挙は、3年ごとに半数の議員を入れ替えるしくみが取られており、今回はその「半数を新しく選ぶタイミング」にあたります。この選挙で選ばれる議員たちは、今後6年間にわたって、制度や法律の審議に関わることになります。
次のセクションでは、参議院という制度そのものの特徴や、6年という任期がもつ意味について整理していきます。
参議院のしくみ──6年関わるから、1票が長く効いてくる

参議院は、国会を構成する二つの議院のうちの一つです。
法律や予算を決める場である国会において、参議院は衆議院と同様に法案を審議し、制度をつくる役割を担っています。しかしその制度設計には、参議院ならではの特徴があります。
任期は6年──長く制度に関わる「安定型」の議院
参議院議員の任期は6年です。これは衆議院の任期(4年)よりも長く設定されています。
さらに、参議院には「解散」がありません。一度選ばれた議員は、原則として6年間そのまま在職し続けます。
このような設計は、「一時的な世論や政局に流されにくく、安定した議論ができる場」としての役割を参議院に持たせているためです。
3年ごとに半数を入れ替える「半数改選制」
参議院は、すべての議員が一度に入れ替わることはありません。
3年ごとに全体の半分ずつを選び直す「半数改選制」が採用されており、今回の選挙もそのタイミングにあたります。
このしくみにより、国会全体のバランスが大きく揺らぐことなく、制度の継続性や議論の積み上げが保たれる構造になっています。
長期の視点から制度を見直す役割
任期の長さと解散のない安定性を活かして、参議院は政策や制度について、より長期的な視点から見直す役割を担っています。また、専門性や良識を重視した人材が選ばれることも多く、「良識の府」と呼ばれることもあります。
衆議院が“政治のスピード感”を担う役割だとすれば、参議院は“慎重な検討”や“制度の調整役”を担う役割といえます。
今回の選挙で選ばれるのは124人
参議院全体の定数は248人です。そのうち半数にあたる124人を選ぶのが、今回の参議院選挙です。
つまり、今回1票を投じる相手は、6年間にわたって国の制度に関わり続ける存在になります。
自分の1票が影響するのは選挙の日だけではありません。
投票によって選ばれた議員は、今後6年間、医療・年金・税制などの制度を形作る場に加わることになります。
次のセクションでは、そうした議員をどうやって選ぶのか──「2枚の投票用紙」を使った選び方について、具体的に見ていきます。
投票用紙は2枚──地域と全国、2つの選び方

参議院議員選挙では、投票所で2枚の投票用紙が配られます。
ひとつは「選挙区選挙」、もうひとつは「比例代表選挙」。
それぞれ選ぶ対象も、決まり方も異なります。
この「2票」を通して、私たちは自分の暮らしに近い地域の課題と、日本全体の方向性の両方に関わることができるようになっています。それぞれの投票が、どんな意味を持っているのかを見ていきましょう。
選挙区選挙──地域の代表を選ぶ1票
1枚目の投票では、自分の住んでいる都道府県を単位とする選挙区から、候補者をひとり選びます。
この選挙は「選挙区選挙」と呼ばれ、地域代表を選ぶものです。
定数(当選者数)は都道府県ごとに異なり、もっとも少ないところでは1人、多いところでは12人が選ばれます。
たとえば、東京都は12人、大阪府や神奈川県は6人、人口の少ない県では1〜2人といった具合です。
地域に根ざした政策や声を届けるには、この選挙で「地元を理解している人」を選ぶことが鍵になります。
合区──小さな県の声を残す工夫
人口の少ない県では、1県だけでは議席を確保しづらくなるため、「合区(ごうく)」という制度が導入されています。
たとえば、鳥取県と島根県、徳島県と高知県は、それぞれひとつの選挙区として扱われます。
これは、地域によって有権者の数に差があるため、1票の重みが不公平になりやすいという問題を調整しつつ、地方の声もきちんと届くようにするための制度的な工夫です。
一方で、「自分の県から候補者が出せない」といった課題もあり、合区は制度の“折り合い”の現れでもあります。
比例代表選挙──全国から選ばれる1票
2枚目の投票では、「政党名」またはその政党が擁立した候補者の「氏名」を記入します。
この選挙は「比例代表選挙」と呼ばれ、全国をひとつの大きな選挙区として、政党の得票数に応じて議席が分配されます。
つまり、自分の地域に関係のない候補者でも、その人の考えや活動に共感すれば全国から応援できるということです。
非拘束名簿式──「人」を応援する投票
参議院の比例代表選挙は、非拘束名簿式を採用しています。
これは、政党が提出する候補者名簿に順位がなく、有権者が名前を書いて投票することで、当選の優先順位が決まる制度です。
たとえば同じ政党の中でも、多くの票を得た候補者が優先的に当選します。
これにより、有権者は政党を通じて投票するだけでなく、その中で特に「この人に行ってほしい」と思う候補を後押しできるようになっています。
2票で支える、2つの視点
この「2枚の投票」は、ただの手続きではありません。
選挙区選挙では地域の声を、比例代表選挙では理念や専門性を、それぞれ国会に届ける役割を持っています。
- 「地元の課題に向き合ってくれる人」を選ぶ1票
- 「この政策を国政で実現してほしい」という思いを託す1票
この2つを通じて、私たちは複雑な社会に対して多面的に意思を示すことができるよう設計されているのです。
制度は、“届きにくい声”をすくい上げる工夫を続けている
選挙の仕組みは決して万能ではありません。
それでも、非拘束名簿式の導入や合区といった制度の工夫は、「どうせ私たちの声は届かない」と感じる心境に、少しずつ応えようとする試みでもあります。
私たちがこうした仕組みを理解し、きちんと使いこなすことこそが、届きにくい声を届くものに変えていく第一歩になります。
次のセクションでは、比例代表制度に込められた「声を拾う仕組み」としての工夫──とくに「特定枠」の意味と限界について整理します。
比例代表と特定枠──届きにくい声を支える仕組み

参院選には、もう一つの投票方法として「比例代表制」があります。
これは、地域に関係なく、全国単位で多様な視点や立場を国会に届けるためのしくみです。
さらに、2019年から導入された「特定枠」は、これまで政治の場に届きにくかった声を制度として反映させるための新たな工夫です。
ここでは、比例代表制と特定枠の意義を整理しながら、社会の多様性をどう政治に反映させるかという視点を考えていきます。
政党にも、候補者個人にも投票できる仕組み
参院選の比例代表では、有権者は政党名だけでなく、候補者個人の名前でも投票できます。
この「非拘束名簿式」によって、同じ政党の中でも得票数が多い候補者から順に当選する仕組みが採用されています。
これにより、全国単位で「この人を応援したい」という気持ちを票として反映でき、地域にとらわれない応援が可能になります。
比例代表制は、政策や理念、専門性などに共感する人を選びやすい制度とも言えます。
特定枠が担う役割と、その背景
非拘束名簿式では、名前を広く知られている候補が有利になる傾向があります。
その一方で、障がいや病気、家庭の事情などにより十分な選挙活動ができない候補者は、名前を書かれる機会が少なくなり、当選が難しくなります。
こうした状況に対応するため、比例代表には「特定枠」が設けられました。
これは、政党が名簿の中であらかじめ優先的に当選させたい候補者を指定できる仕組みです。
実際には、重度の障がいがある人や非正規雇用の当事者、マイノリティ当事者など、これまで国会に届きづらかった現場の声を代表する候補者が指定される例が増えています。
「票になりにくい声」も、制度で支えようとする姿勢
特定枠によって、すべての立候補者が同じ土俵で競えない現実に対して、制度の側から調整が試みられています。
それは「票になりにくい声」をすくい上げるための、構造的な補助装置とも言えます。
もちろん、特定枠の選定基準や透明性には今後の検討課題もあります。
それでも、制度が少しずつ現実に近づこうとしている動きがあることは、私たちの1票の意味を考えるうえで重要な視点です。
「誰を選ぶか」だけでなく、「どんな声を届かせたいか」
比例代表の投票は、単に「この政党に入れたい」という選択だけではありません。
その票を通して、「社会のどの現実にもっと目を向けてほしいか」を示すことができます。
政党名だけでなく、候補者名で投票するという選び方も含めて、比例代表制は「社会の多様な声を、どう届けるか」を考える機会でもあります。
この仕組みを正しく理解し、活用することが、届きにくかった声を政治の場につなげていく確かな一歩につながります。次のセクションでは、「どうせ変わらない」と感じて選挙に行かないことで、何が決まってしまうのか──行かないという選択が持つ意味について整理していきます。
「どうせ変わらない」?──行かないことで何が決まってしまうのか

「選挙に行っても何も変わらない」と感じる声は、今の日本ではかなり多いと思います。実際、政治への不信感や個々人の無力感から、投票所へ足を運ばない人が一定数存在しています。
しかし、私たちが投票を見送ったとき、政治はその空白を黙って受け入れるのではなく、誰かの声だけをもとに動いていくという現実があります。
ここでは、選挙に「行かない」という選択が、私たち自身の生活や社会にどう関わっているのかを考えます。
投票率が低いと、偏った意見だけが反映される
選挙では、投票された票のみによって議席が決まります。
つまり、行かなかった人の考えや不満は、何もカウントされないということです。
たとえば、組織票や固定の支持層を持つ団体は、投票率が低ければ低いほど相対的に有利になります。
結果として、特定の層の要望ばかりが反映され、静かにしていた人たちの不満は置き去りにされてしまうのです。
- 「若い世代の声が反映されにくい」
- 「非正規雇用や子育て当事者の立場が見えづらい」
こうした状況も、投票に行かないことが積み重なった結果だと言われてしまうわけです。
行かなかった1票が、「反対」としては数えられない
ある政策に不満があっても、選挙に行かずにいるだけでは、その意思が可視化されることはありません。
選挙では「賛成」と「反対」が票で表され、行かなかった人の考えは、反対にもカウントされないのです。
- 賛成:10票
- 反対:8票
- 行かなかった人:82人
このような場合、実際には多くの人が様子を見ていたとしても、制度の上では「賛成多数」として進んでいきます。
制度上、意思を示さないという選択は、結果的に現状を肯定する扱いをされてしまうのです。
選挙結果は、生活に直接つながっている
選挙で選ばれた議員は、法律や予算、制度の見直しなどを話し合い、実行に移す立場にあります。
つまり、医療費の自己負担割合や、教育予算の配分、雇用制度の整備など、私たちの暮らしに直結する内容が日々決められているということです。
選挙に行くかどうかは、政治に関心があるかどうかだけの話ではありません。
「これからの生活で何を大事にしたいか」という価値観を、間接的に社会に届ける手段でもあります。
「変わらない」ままでいいのか、を問い直す
「変わらない」という思いが広がる背景には、これまでの政治に対する失望や諦めもあるでしょう。
それでも、選挙に行くことでしか、制度の方向性に関わることはできません。
投票は、「正しい答え」を見つける行為ではありません。
むしろ、「どういう方向で話し合ってほしいか」「どんな声を拾ってほしいか」を、私たちの側から示すことに意味があります。
次のセクションでは、選挙に行くことが、なぜ「暮らしの優先順位」を示す行動につながるのかを考えていきます。
選挙に行くことは、暮らしの優先順位を示すこと

選挙は、社会のどこに力を注ぐべきかを、私たち自身が示す機会です。
候補者や政党が掲げる政策には、「税金をどこに使うか」「どんな制度を整えるか」といった具体的な判断や配分の意図が含まれています。
その判断は、自分自身の暮らしや関心に直結しています。
このセクションでは、選挙を通じて私たちの意見や関心がどのように制度に反映されるのかを整理し、その仕組みが暮らしにどう影響しているかを見ていきます。
政策は「資源の配分」の意思決定
政治が扱う課題には、教育、医療、労働、子育て、物価対策、防災、財政など多岐にわたる分野があります。
限られた財源のなかで、どの分野を優先するか、どこに予算や制度の手当を厚くするかは、政府や国会によって決定されます。
選挙においては、それぞれの候補者や政党が優先したい政策や制度設計を公約に掲げています。
私たちが誰に票を託すかは、こうした優先順位の中で、どの方向性を支持するかを明確に示すことになります。
投票は、個人の価値観を制度に反映させる手段
選挙に参加するかどうかは、政治に関心があるかどうかだけでなく、自分の暮らしに関わる課題にどう向き合うかという姿勢にも関わります。
たとえば、
- 子育て支援に力を入れる候補に票を託すことは、保育環境や教育制度への関心を表明することにつながります。
- 物価や賃金の問題に対する対策を重視する候補を選ぶことは、家計や労働環境に対する意思を伝える手段になります。
このように、投票は「誰かのため」ではなく、「自分が社会に何を求めるか」を制度に対して明確に示す機会です。
迷いがあっても、意思を示すことに意味がある
どの候補者や政党が最善かを判断するのは簡単ではありません。
公約や発言の内容を見比べても、すべてに納得できる選択肢が見つからないこともあるでしょう。
しかし、選挙は正解を当てるものではなく、自分が何を大切にしたいかを考える行動です。
完全に一致する候補がいなくても、「少しでも近い方向性」を選ぶことには十分な意味があります。
次のセクションでは、ここまで見てきた制度と選挙の意味をあらためて整理し、私たちの暮らしと政治との接点をもう一度捉え直します。
まとめ:政治との距離を、しくみから見直す
参議院議員選挙は、ふだん意識しにくい「国の制度のつくり方」と、私たちの暮らしとのつながりを見直すきっかけになります。
日々の生活に直接関わる制度の多くは、国会での議論と決定を通じて形づくられています。参議院はその国会の一翼を担い、法律や予算案の慎重な審査や、見直しを行う役割を持つ機関です。
選挙では、「どの政党や候補者に託すか」という選択を通じて、社会のどこに力を注いでほしいか、どんな課題を優先してほしいかという意思を表明することができます。
これは、制度の仕組みの中で私たちに与えられている、数少ない「政治に直接関わる手段」の一つです。
選挙の制度は決して万能ではありません。一票の格差や、声の届きにくさといった課題も残っています。
それでも、比例代表制度や特定枠、合区といった仕組みには、多様な声を反映させるための工夫が重ねられています。
選挙を通じて制度を正しく理解し、自分なりの判断を持つこと。
それは、「誰に入れるか」を考える行動であると同時に、「どう社会に関わっていくか」を考える入口でもあります。



よくある質問
参院選ってなんですか?
参院選とは、「参議院議員選挙」の略で、国会の一部を構成する参議院の議員を選ぶための選挙です。
社会保障や税制、教育、労働といった制度を話し合い、形にしていく役割を持つ参議院のメンバーを、全国の有権者が選びます。今回は、その議員の半数を選び直す機会です。
ほかにも国会議員を選ぶ選挙はあるのですか?
あります。もう一つは「衆院選(衆議院議員選挙)」です。
日本の国会は「参議院」と「衆議院」の二つの議院で構成されていて、それぞれで議員を選ぶ選挙が実施されます。
衆院選との違いはなんですか?
大きく違うのは、任期・役割・制度設計です。
- 参院選:任期は6年で、解散はありません。3年ごとに半数を選び直します。
- 衆院選:任期は4年ですが、内閣の判断で「解散」があり、選挙が前倒しされることがあります。
参議院は制度を落ち着いて見直すための「安定型」、衆議院は政権選択を通じて政策を前に進める「推進型」の役割を担っています。
選挙に行っても何も変わらない気がします。それでも意味はありますか?
選挙は、「今の社会に何を望むか」を示す唯一の手段です。
たとえ1票で大きな変化が起きなくても、積み重ねによって政策の優先順位が変わるきっかけになります。
また、行かないことで「賛成」と見なされてしまうのが制度の仕組みです。
誰に入れればいいのか分かりません。どうしたらいいですか?
まずは、各候補者や政党が発表している政策や活動内容を調べてみましょう。
「自分が大切にしたいこと」を起点に、どの方向性に近いかを考えてみることが大切です。
完全に一致する候補がいなくても、「少しでも近い」と思える選択をすることには十分意味があります。
投票率が低いと、どんな問題が起きるのですか?
特定の層や団体の意見だけが通りやすくなり、社会全体の声が偏ってしまう恐れがあります。
たとえば、若年層の投票率が低ければ、その世代の課題(教育、雇用、子育てなど)は後回しにされやすくなります。
どの政党を選んだらいいのか、どう見極めればいいですか?
各政党の公式サイトや比較サイトで公約を読み比べるのがおすすめです。
また、「この分野に力を入れてほしい」という視点から候補者や政党を選ぶのも一つの方法です。
投票所では何をどうやって選ぶのですか?
参院選では2枚の投票用紙が配られます。
- 1枚目(選挙区選挙):自分の都道府県から立候補している候補者を1人選びます
- 2枚目(比例代表選挙):政党名または政党が推薦する候補者名を記入します
それぞれ、地域と全国の視点から選ぶ構成です。
合区ってなんですか?
人口が少なく、単独の県としてでは議席を確保しづらい県同士をひとつの選挙区にまとめた制度です。たとえば鳥取県と島根県、徳島県と高知県などが対象で、「地方の声がかき消されないようにする」ための制度的工夫です。
特定枠ってなんですか?
比例代表制において、政党が「優先的に当選させたい候補者」を名簿の上位に固定できる制度です。名前を書かれづらい立場の候補(障がいのある人、非正規雇用の当事者など)を制度的に後押しする役割を持っています。
非拘束名簿式ってなんですか?
比例代表で「政党名」か「候補者名」のどちらでも投票できる仕組みです。候補者名で多く票を集めた人が、政党内で優先的に当選するため、有権者の意思がより細かく反映されます。
.webp)