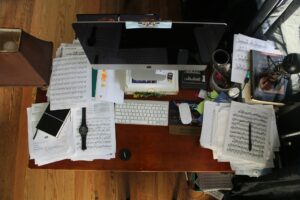日本には、花を愛でる文化が古くから根づいています。
花見の起源は、奈良時代に梅の花を鑑賞する風習に見ることができます。そこから平安時代以降、桜が春の象徴として親しまれるようになり、花を楽しむ行事として、次第に人々の暮らしに根づいていきました。時代ごとに異なる風景と価値観の中で、「花見」は春を迎えるよろこびの象徴として、時には格式ある行事として、時には庶民の楽しみとして、その姿を変えてきたのです。
本記事では、梅を愛でた奈良時代から、桜が美の象徴となった平安時代、武士の間に広がった鎌倉時代の春、秀吉の豪奢な宴が彩った桃山文化のひととき、そして庶民文化として花開いた江戸時代の賑わいまで、
日本人と花見の歴史を、時代の流れとともにたどっていきます。
桜を見上げるたび、先人たちは何を想い、何を重ねてきたのか。
その文化の足跡に心を重ねながら読み進めてみてください。
奈良時代のはじまり:梅とともに歩み出した花見の原型

花見の歴史は、奈良時代(710年〜794年)にまでさかのぼります。
この時代、春の花といえば桜ではなく、梅が中心でした。中国から伝わった文化や美意識の影響を受け、当時の日本では、梅の花を鑑賞することが貴族の間で定着していきました。
中国文化の影響と梅の位置づけ
梅の鑑賞文化は、遣唐使などを通じて中国から伝わったものです。唐の詩文に親しんでいた貴族たちは、その様式を取り入れ、梅の咲く庭で詩を詠み、宴を開くことを楽しんでいました。
梅の木は香り高く、寒さの中でいち早く花を咲かせることから、季節の移ろいを感じる象徴として大切にされていました。また、神聖な木とされることもあり、庭園や寺社などに意図的に植えられることもありました。
『万葉集』に見られる梅の存在
奈良時代の代表的な歌集『万葉集』には、梅の花を詠んだ歌が多く収められています。春の喜びや自然の美しさを梅に託し、言葉で表現する文化がこの時代にはすでに根づいていたことがわかります。
一方、桜を詠んだ歌はごく少数にとどまっており、当時の日本においては、桜よりも梅のほうが文化的に重要な位置を占めていたことがうかがえます。
桜への関心の芽生え
奈良時代の後半になると、桜への関心も少しずつ見られるようになります。とはいえ、当時の桜は「山に咲く花」という認識が強く、梅のように庭で愛でる対象ではありませんでした。
桜が花見の中心となるのは、平安時代以降のことです。この時代に芽生えはじめた関心が、後の桜文化の土台となっていきます。
奈良時代における花見は、梅の花を囲む静かな文化的営みとして始まりました。
そのなかで育まれた自然観や季節感が、のちに桜を中心とする花見文化へとつながっていきます。
平安時代の転換期:桜が春の主役となった時代

奈良時代には梅が花見の中心でしたが、平安時代(794年〜1185年)に入ると、桜が次第に人々の関心を集めるようになります。
この時代、宮廷文化が成熟し、自然の美しさを言葉や儀式に取り入れる傾向が強まるなかで、桜は春の象徴として定着していきました。この時の桜は、ヤマザクラが中心であったとされています。
宮中行事としての花見
桜を中心とした花見が公式な行事として記録に現れるのは、820年に嵯峨天皇が催した「花宴の節(かえんのせつ)」です。
この宴では、満開の桜の下で和歌を詠むことが主な目的とされており、花見が文学や芸術と深く結びつくきっかけとなりました。
以降、春の花を楽しむ行事としての花見は、宮中や貴族社会の年中行事として定着していきます。
和歌に詠まれた桜
平安時代の文学作品には、桜を題材とした和歌が数多く見られます。在原業平の
「世の中にたえて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし」(『古今和歌集』)
という歌は、桜の存在が春の気持ちに影響を与えるほど、強い存在感をもっていたことを示しています。
桜はその儚さと美しさによって、「散ること」を含めて愛される花となり、自然の美と感情を重ね合わせる象徴的な存在となりました。
鑑賞から表現へ
この時代の花見は、ただ花を鑑賞するだけでなく、花を通して自然の移ろいや個人の感情を表現する文化的な営みへと発展していきます。
貴族たちは、桜のもとで和歌を詠み、音楽や舞を楽しみながら季節を迎えました。花見は詩歌や芸能と結びつき、視覚的な美しさだけでなく、言葉や形式を通じて春を味わう行為として受け継がれていきます。
平安時代に桜が花見の中心となったことで、花を愛でるという行為は、より多面的な文化へと展開していきました。
この時代に確立された桜の象徴性は、のちの日本文化の中でも長く生き続けることになります。
鎌倉時代の広がり:武士の間に根づいた花見の風習

平安時代に宮廷行事として定着した桜の花見は、鎌倉時代(1185年〜1333年)に入ると、武士階級の間にも広がりを見せます。武家政権の成立により、政治や文化の中心が貴族から武士へと移行していく中で、花見の風習もまた、新たな層に受け継がれていきました。
このあたりから、シダレザクラやエドヒガンなどが出てきます。また、八重桜が普及し出したのも鎌倉時代とされています。
花見を通じた教養と交流
鎌倉時代の武士たちは、単なる軍事的存在ではなく、礼儀や和歌などの教養も重視していました。花見は、自然を楽しむ場であると同時に、教養を磨き、社交を深める機会としても利用されました。
貴族のように詩歌を詠むことが奨励され、桜のもとでの花見は、形式こそ異なれど、文化的な側面をもつ行事として受け継がれていったのです。
寺社と桜の風景
この時代、京都を中心に寺社や山々に桜が多く植えられ、花見の場として整えられるようになります。東山や嵐山などは、平安時代からの名所として引き続き親しまれ、また、新たな桜の名所も少しずつ生まれていきました。
寺院の境内や山のふもとに咲く桜は、自然を感じる場所であると同時に、人々が信仰を寄せる場でもあり、日常の中で親しまれる花見の場として、自然・信仰・暮らしが一体となった風景として定着していきました。
武士らしい花見のかたち
武士の花見は、貴族のそれと比べて、より実用的で簡素な面もありました。
桜のもとで酒を酌み交わし、親しい者同士で語らうような、私的で日常的な楽しみ方が重視されるようになります。
また、武士の集まりの場では、剣術や弓術を披露し合う場面もあり、花見が非公式な交流や訓練の機会を兼ねることもありました。
鎌倉時代の花見は、上層階級の教養文化としての側面を保ちながらも、より広い層の人々へと少しずつ広がっていきました。この時期の変化は、後に続く桃山文化や江戸時代の花見文化の展開へとつながっていきます。
桃山文化の頂点:豊臣秀吉と醍醐の花見

桃山文化(16世紀後半)は、戦国の混乱を経て日本統一が進められた時代であり、政治権力と文化が大きく交差した時期でもあります。通常は安土桃山時代と表記されますが、今回は秀吉の治めた期間にスポットを当てて桃山文化と記載します。
その象徴的な出来事のひとつが、豊臣秀吉による大規模な花見の宴でした。花見はこの時代、政治的演出と娯楽を兼ね備えた公的かつ文化的な催しとして発展します。
醍醐の花見とその背景
1598年、秀吉は京都・醍醐寺で「醍醐の花見」と呼ばれる大規模な花見の宴を開催しました。
この行事には、側近や大名、貴族、女性たちなど約1300人が招かれ、整備された境内に咲く桜のもとで、盛大な宴が繰り広げられました。
- 会場の準備
この花見のために、醍醐寺の境内には新たに数百本の桜が植えられたとされ、景観そのものが政治的な演出の一部となっていました。 - 豊臣政権の誇示
華やかな催しは、平和の象徴としての桜と、秀吉の統治力を国内に示すための手段でもありました。
芸能・詩歌・贈答の場としての花見
この花見では、単に桜を鑑賞するだけでなく、詩歌の詠み交わしや舞の披露なども行われました。
秀吉自身も詩を詠み、参加者の中には即興で詩を交わす者もいたとされています。花見は芸能や言葉を通じた文化的交流の場でもありました。
また、参加者には衣装の準備が命じられ、装いにも気を配るよう指示があったと伝えられています。これにより、花見は視覚的な華やかさと儀礼性を備えた政治的舞台となっていきました。
花見の意味の広がり
秀吉の花見は、それまでの貴族的な文化とも、武士の日常的な行楽とも異なる、新しい様式を提示しました。
それは、桜のもとに人々を集め、自身の権威と文化的影響力を広く示す手段としての花見でした。
醍醐の花見は、花見を政治的・文化的な演出として用いた初めての大規模行事とされています。
その形式や意図は、後に庶民文化として花見が広がっていく際のひとつの土台となりました。
江戸時代の定着:花見が庶民文化として根づいた時代

江戸時代(1603年〜1868年)は、長期にわたる平和のもとで庶民文化が大きく発展した時代です。
それまで貴族や武士の間で行われてきた花見は、この時期に一般市民の間にも広がり、春の風物詩として定着していきました。八重桜の品種が増えたのは江戸時代とも。
江戸時代は古典園芸にも代表されるように、園芸が盛んな時代でもあり、そのことがより庶民への花見の浸透を促しました。
将軍の政策と桜の名所づくり
花見の大衆化の背景には、幕府による都市整備や景観政策が関係しています。とくに徳川吉宗は、享保の改革の一環として各地に桜の名所を整備しました。
- 上野の山(現在の上野恩賜公園)
寛永寺の境内に桜を植樹し、多くの人が訪れる花見の名所となりました。 - 隅田川沿い(現在の隅田公園)
水辺と桜の景観が親しまれ、庶民の行楽地としてにぎわいを見せました。 - 飛鳥山公園
将軍の命により整備された場所であり、庶民が気軽に花見を楽しめる場として人気を集めました。
こうした名所の整備によって、桜は身近な存在となり、花見は特別な階級だけでなく、誰もが楽しめる年中行事となっていきます。
庶民が楽しんだ花見の風景
江戸の庶民にとって、花見は単なる鑑賞の場ではなく、家族や友人と共に過ごす行楽のひとときでした。
- 食事と酒
弁当や酒を持ち寄り、桜の下でにぎやかに宴を開くスタイルが広まりました。花見団子や桜餅など、花見にちなんだ食文化もこの頃に定着していきます。 - 芸能と余興
場所によっては、踊りや唄、即興の芝居などが行われ、花見は町人文化の一部としても発展しました。 - 場所取りと賑わい
桜の開花に合わせて人々が早朝から場所を確保し、日中から夕方にかけて桜の下に人々が集う様子は、江戸の春の風景として定番となっていきました。
ソメイヨシノの登場
江戸時代後期には、現在もっとも広く親しまれている桜の品種「ソメイヨシノ」が誕生します。
染井村(現在の東京都豊島区)で作出されたと言われるこの品種は、淡い花色と一斉に咲く性質が評価され、短期間で全国に広がっていきました。
- 一斉開花による視覚効果
多くの木が同時に満開を迎えることで、花見の時期が読みやすく、風景としての統一感も生まれました。 - 観賞用に特化した品種
実をつけず、花を咲かせることに特化したこの桜は、まさに花見文化に最適な品種として歓迎されました。
江戸時代には、花見は春を祝う行楽として庶民の間に深く浸透しました。
この時代に確立された花見のかたちは、現代に至るまで変わることなく受け継がれています。
まとめ|花見という文化が映してきたもの
花見は、単に花を楽しむ行事ではなく、時代とともにそのかたちを変えながら、日本人の暮らしや価値観の中に深く根づいてきました。
奈良時代には梅を愛でる風習として始まり、平安時代には桜が春の象徴となり、文学や芸術と結びついて発展しました。鎌倉時代には武士の間に広がり、桃山文化では政治と文化の舞台として大規模な宴が催され、江戸時代には庶民の行楽として広く親しまれるようになります。
それぞれの時代において、花見は人々の心のあり方や社会のありようを映し出してきました。そして現代においても、桜の下に集い、季節を感じる時間は、多くの人々にとって変わらぬ春の風景となっています。
過去に咲いた花々が、今の私たちの記憶の中にも重なっているように、花見の歴史はこれからも静かに受け継がれていくのかもしれません。



よくある質問
花見はいつごろから始まったのですか?
日本における花見の起源は奈良時代にさかのぼります。当時は桜ではなく、梅の花を鑑賞することが中心でした。花を愛でながら詩を詠み、宴を開く文化が貴族のあいだで広まっていきました。
桜が花見の主役になったのはなぜですか?
平安時代に入ると、宮中行事として桜の花見が定着し、桜が春の象徴として扱われるようになりました。桜のはかなさや美しさが、当時の文学や美意識と強く結びついたことが、その背景にあります。
豊臣秀吉の「醍醐の花見」とは何ですか?
1598年、豊臣秀吉が京都・醍醐寺で開催した大規模な花見の宴を指します。約1300人が招かれ、詩歌や舞などの文化的催しも行われました。花見が政治的演出と結びついた代表的な事例とされています。
庶民が花見を楽しめるようになったのはいつ頃ですか?
江戸時代に入り、将軍や幕府による都市整備の一環として桜の名所が各地に整えられたことで、花見は庶民の行楽として定着しました。弁当を持って出かけるスタイルや、桜餅・花見団子などの食文化もこの時期に広がりました。
ソメイヨシノはいつ誕生したのですか?
江戸時代後期、現在の東京都豊島区にあたる染井村で作出されたとされています。一斉に開花する特徴があり、花見のタイミングを計りやすいことから、現代においても最も広く親しまれている桜の品種です。
おまけ①:ソメイヨシノの登場と、花見文化の転換点
江戸の後期、花見が庶民に広がりを見せるなか、ひときわ印象的な桜が登場しました。それが、現在日本で最も多く親しまれている品種「ソメイヨシノ」です。この桜の出現は、花見という年中行事の性質に大きな変化をもたらすことになります。
染井村で生まれた桜
ソメイヨシノは、江戸時代後期に染井村(現在の東京都豊島区駒込周辺)の植木職人によって作出されたとされます。交配のもとになったのは、エドヒガンとオオシマザクラ。桜の名所として知られた吉野山にちなみ、当初は「吉野桜」と呼ばれていましたが、後に混同を避けて「ソメイヨシノ」と名づけられました(明治時代のことです)。
ただし、当時は花粉という概念がまだなかったこともあって、人為的に作られたのではなく、自然交雑により偶然誕生したのではないかとも言われています。
一斉開花の視覚的インパクト
ソメイヨシノは接ぎ木によって同一の遺伝子をもつ木々が全国に広まったため、開花の時期が揃いやすいという特性をもちます。これにより、花見の日程を立てやすくなるだけでなく、一面が花に染まるような統一された景観が生まれました。この「一斉開花」は、観る者に強い印象を残す花見の風景をつくり出します。
つまり、全てクローンなのです。すごいよね、クローンで
観賞に特化した品種としての魅力
ソメイヨシノは実をつけにくく、花だけを楽しむために最適な品種です。また、葉よりも先に花が咲くため、満開時には葉に邪魔されることなく、花そのものが視界を埋め尽くします。その潔さ、儚さは、桜に込められた日本人の美意識とも深く共鳴し、多くの人に受け入れられました。
花見文化への影響
このようにしてソメイヨシノは、花見を季節の象徴として定着させるだけでなく、年中行事としての性質を視覚的・時間的に明確化した桜ともいえます。江戸の花見が都市に根づいた娯楽であったなら、ソメイヨシノの普及はそれを「全国的な文化」へと押し広げる力を持っていました。
おまけ②:花見に用いられた桜の変遷
現代ではソメイヨシノが桜の代名詞のように語られますが、そこに至るまでの花見文化には、時代ごとに異なる桜の品種が登場し、親しまれてきた歴史があります。
それぞれの桜が咲いていた風景には、その時代の人々の価値観や暮らしぶりが滲んでいました。
平安から中世:自然の桜、ヤマザクラの時代
古くは、奈良・吉野山に見られるヤマザクラ(山桜)が花見の代表でした。
白から淡紅色の花が、赤みを帯びた若葉とともに開く姿は、自然の中に溶け込むような美しさを持ち、和歌や物語の中でもたびたび詠まれています。
この頃の花見は、貴族たちが歌を詠み、春の訪れを愛でる風雅な遊びであり、信仰や山岳風景とも結びついたものでした。
中世から近世:寺社や庭園に咲く枝垂桜と彼岸桜
戦国・安土桃山時代を経て江戸時代に入ると、花見の場は次第に寺社や庭園、城下の名所へと広がっていきます。
この時期に多く用いられたのが、シダレザクラ(枝垂桜)やエドヒガン(江戸彼岸)。
特に枝垂桜は、京都・円山公園や各地の寺院境内で人々を魅了し、優雅で落ち着いた雰囲気の花見が展開されました。
また、エドヒガンは樹齢が長く、古木が多く見られる品種で、寺社の境内や山間部に植えられ、信仰や供養の場に寄り添う桜として人々に親しまれていました。
江戸中期以降:園芸の発達と品種の多様化
江戸中期には都市の発展とともに園芸文化が庶民の間にも広まり、桜の品種にも多様性が生まれます。
カンヒザクラ(寒緋桜)など、南方系の品種が植木市や園芸家の手で一部に導入され、桜の季節や花色の幅が広がっていきました。
ただし、この頃までは、「開花の時期や咲き方が異なる複数の品種が混在する花見」が一般的でした。
今のような「一面が同じ桜に染まる」光景は、まだ生まれていません。
江戸後期:ソメイヨシノ誕生前夜
こうした流れのなかで、江戸時代後期に誕生したのがソメイヨシノです。
その特性は「葉よりも先に咲く」「観賞に特化」など、従来の桜とは異なるものでした。
のちに接ぎ木によって同一個体が広く増やされたことで、多くの木が一斉に開花するという、これまでにない風景を生み出す品種花見のスタイルそのものが大きく変わる転機を迎えることになります。
.webp)