2025年– date –
-
無駄なことは本当に無駄なのか|意味のない時間が持つ役割
 自分にとって役に立つこと。誰かにとって役に立つこと。自分にとって意味があること。誰かにとって意味があること。私たちは日々、そうした基準で行動を無意識に選んでしまいがちです。無駄を避け、効率よく歩むことは、社会で生き抜くうえではとても自然な姿勢でもあります。そのため、何もしなかった時間を「無駄」と決めつけてしまうどころか、振り返ったときに後悔さえもしてしまいます。それでも、そうした時間が、なぜか記憶から消えずに残ることがあります。では、無駄なことは、本当に無駄なのでしょうか...
自分にとって役に立つこと。誰かにとって役に立つこと。自分にとって意味があること。誰かにとって意味があること。私たちは日々、そうした基準で行動を無意識に選んでしまいがちです。無駄を避け、効率よく歩むことは、社会で生き抜くうえではとても自然な姿勢でもあります。そのため、何もしなかった時間を「無駄」と決めつけてしまうどころか、振り返ったときに後悔さえもしてしまいます。それでも、そうした時間が、なぜか記憶から消えずに残ることがあります。では、無駄なことは、本当に無駄なのでしょうか... -
なぜ、ちゃんと話しているのに遮られるのか──「結論を急ぐ人」と会話が噛み合わない本当の理由
 話の途中で、こう言われたことはありませんか。「で、何が言いたいの?」「つまり結論は?」こちらは順を追って説明していただけなのに、その一言で拒絶されたような気がして、言葉を探していた頭の中が一瞬で真っ白になってしまう。そしてあとから、「自分の話し方が悪かったのかもしれない…」とモヤモヤ。このやり取りは、割と多くの人が経験しており、職場でも、家族との会話でも、親しい人とのやり取りの中でも起こってしまうものです。しかも厄介なのは、相手が怒っているわけでも、冷たくしているわけでもな...
話の途中で、こう言われたことはありませんか。「で、何が言いたいの?」「つまり結論は?」こちらは順を追って説明していただけなのに、その一言で拒絶されたような気がして、言葉を探していた頭の中が一瞬で真っ白になってしまう。そしてあとから、「自分の話し方が悪かったのかもしれない…」とモヤモヤ。このやり取りは、割と多くの人が経験しており、職場でも、家族との会話でも、親しい人とのやり取りの中でも起こってしまうものです。しかも厄介なのは、相手が怒っているわけでも、冷たくしているわけでもな... -
ブログを1年間しっかりとやってみて感じたこと
 このブログも気付けば、記事数はなんと300件にもなっていました。(書き溜めた下書きを入れて、ですが)始めたての頃はブログという言葉は聞いたことがあるものの、右も左もわからず。ただただ、「なんかブログで稼いでいる人が居るらしい」という情報だけで、当時会社員であったわたくしは藁にも縋る思いで、副業になるのならばやってみよう!という浅はかな考えでスタートしたのでした。「WordPressってなんだい?」「どうやって操作するの??」「え?ブログ名考えなきゃいけないのか…。」「書きたいことぉ!?...
このブログも気付けば、記事数はなんと300件にもなっていました。(書き溜めた下書きを入れて、ですが)始めたての頃はブログという言葉は聞いたことがあるものの、右も左もわからず。ただただ、「なんかブログで稼いでいる人が居るらしい」という情報だけで、当時会社員であったわたくしは藁にも縋る思いで、副業になるのならばやってみよう!という浅はかな考えでスタートしたのでした。「WordPressってなんだい?」「どうやって操作するの??」「え?ブログ名考えなきゃいけないのか…。」「書きたいことぉ!?... -
【お知らせ】「大吉しか出ない」おみくじページを作ってみました
 皆さま、いつもありがとうございます!今度はですね、「大吉しか出ないおみくじ」を作成してみました。 大吉しか出ないおみくじページを作ってみたので、ぜひ遊んでみてくださいませ・場所はトップページの下のほうの水たまり横の画像をクリックorタップ・名前は「祈弥の社(はふりみのやしろ)」。← こちらのリンクからもいけます・スクロールに合わせて動くアニメーション(?)にしています・1日1回しか引けず、再アクセスすると引き終わった筒だけの状態になってます。 (昼と夜とで背景変えてみました)・お...
皆さま、いつもありがとうございます!今度はですね、「大吉しか出ないおみくじ」を作成してみました。 大吉しか出ないおみくじページを作ってみたので、ぜひ遊んでみてくださいませ・場所はトップページの下のほうの水たまり横の画像をクリックorタップ・名前は「祈弥の社(はふりみのやしろ)」。← こちらのリンクからもいけます・スクロールに合わせて動くアニメーション(?)にしています・1日1回しか引けず、再アクセスすると引き終わった筒だけの状態になってます。 (昼と夜とで背景変えてみました)・お... -
雨音で集中力が高まる?記憶力にも良い影響がある理由と活用法
 雨の日になると、いつもよりも落ち着いて作業ができるように感じたり、頭の切り替えがしやすく感じたりしませんか?既にご存知の方も多いかもしれませんが、これは気のせいなんかではありません。雨音が心や認知機能に働きかける可能性が、いくつかの研究で示されているのです。雨音には「1/fゆらぎ」や「自然音特有のリラックス効果」、そして「雑音を覆い隠すマスキング効果」などの特徴があります。この記事では、雨音が集中力や記憶力に関与する仕組みを整理し、日常で活かせる方法をご紹介します。日常の作業...
雨の日になると、いつもよりも落ち着いて作業ができるように感じたり、頭の切り替えがしやすく感じたりしませんか?既にご存知の方も多いかもしれませんが、これは気のせいなんかではありません。雨音が心や認知機能に働きかける可能性が、いくつかの研究で示されているのです。雨音には「1/fゆらぎ」や「自然音特有のリラックス効果」、そして「雑音を覆い隠すマスキング効果」などの特徴があります。この記事では、雨音が集中力や記憶力に関与する仕組みを整理し、日常で活かせる方法をご紹介します。日常の作業... -
スピリチュアルは電磁波を用いることで科学的に説明できる日が来るのではないか?
 スピリチュアルと言われる現象の多くは、まだ科学で扱いきれていない領域に置かれています。あるいは、科学的に見えても、都合の良い科学をあてがっただけで一切の本質を捉えきれていないものもあるかもしれません。しかし、世界の成り立ちを見ていくと、科学と完全に切り離された別物とも言いきれない感覚があります。また、スピリチュアルそのものを否定してしまうと、そもそもの日本での文化が成立しないような気もしています。私たちは何を「科学」と呼び、何を「スピリチュアル」と分けているのでしょうか。...
スピリチュアルと言われる現象の多くは、まだ科学で扱いきれていない領域に置かれています。あるいは、科学的に見えても、都合の良い科学をあてがっただけで一切の本質を捉えきれていないものもあるかもしれません。しかし、世界の成り立ちを見ていくと、科学と完全に切り離された別物とも言いきれない感覚があります。また、スピリチュアルそのものを否定してしまうと、そもそもの日本での文化が成立しないような気もしています。私たちは何を「科学」と呼び、何を「スピリチュアル」と分けているのでしょうか。... -
「なるほど」と言うだけで理解が深まる? 頷きと相槌が生む“認知の効果”をわかりやすく解説
 勉強で講義動画を見ているときや相手の話を聞くときに無意識に「うんうん」と頷いたり、納得した瞬間には「なるほど」と口にする。意識せず自然と行っているこの動作には、実は“理解の深まり方に影響する仕組み”があるようです。ただ聞くだけのときと、頷きや相槌を交えながら聞くときとでは、頭に残る情報の質が変わる…、と。それはどういうことなのでしょうか?本記事では、とりわけよく使いがちな相槌である「なるほど」という短い言葉を例に、脳が内容をどう整理し、どのように意味づけているのかを見ていきた...
勉強で講義動画を見ているときや相手の話を聞くときに無意識に「うんうん」と頷いたり、納得した瞬間には「なるほど」と口にする。意識せず自然と行っているこの動作には、実は“理解の深まり方に影響する仕組み”があるようです。ただ聞くだけのときと、頷きや相槌を交えながら聞くときとでは、頭に残る情報の質が変わる…、と。それはどういうことなのでしょうか?本記事では、とりわけよく使いがちな相槌である「なるほど」という短い言葉を例に、脳が内容をどう整理し、どのように意味づけているのかを見ていきた... -
月の満ち欠けと農業の科学的な関係|作物の成長と農作業タイミングを根拠から読み解いてみる
 月の満ち欠けが農業に影響するという話を聞いたことがある人は多いかもしれません。しかし、それは迷信なのでしょうか?それとも、実際に科学的な根拠がある現象なのでしょうか?本記事では、月の引力や植物の水分移動といった生理学的なメカニズムに着目し、月のリズムが作物の成長や収穫タイミングにどのように関係するのかを、論理的に考察していきます。さらに、各月齢に適した農作業のタイミングや、再現性のある農法として注目されている実践例もご紹介。感覚や経験則にとどまらず、「なぜそうなるのか?」...
月の満ち欠けが農業に影響するという話を聞いたことがある人は多いかもしれません。しかし、それは迷信なのでしょうか?それとも、実際に科学的な根拠がある現象なのでしょうか?本記事では、月の引力や植物の水分移動といった生理学的なメカニズムに着目し、月のリズムが作物の成長や収穫タイミングにどのように関係するのかを、論理的に考察していきます。さらに、各月齢に適した農作業のタイミングや、再現性のある農法として注目されている実践例もご紹介。感覚や経験則にとどまらず、「なぜそうなるのか?」... -
【お知らせ】『なんかよくわかんないやつの居るところ』を作りました
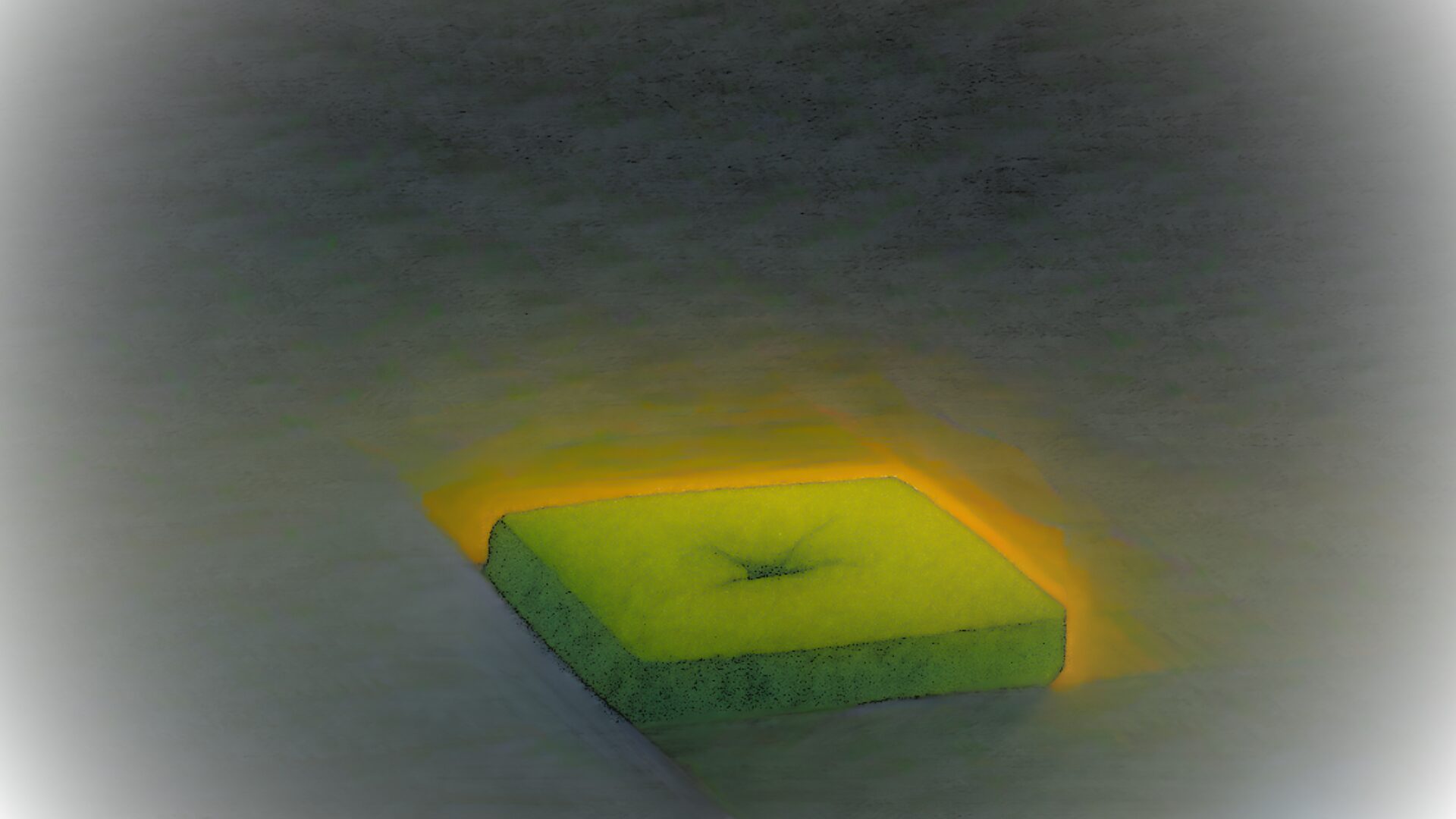 『なんかよくわかんないやつの居るところ』というページを作ってみました。・場所はサイドバーの右下のほう(スマホだとページの下のほう)の座布団の画像をクリック(こちらからもいけます 👉️ なんかよくわかんないやつの居るところ)・17:00〜翌4:59のいわゆる夜だけ“やつ”を構うことができます。・キャラクターをクリックorタップすると、ただただセリフが出るだけのページです。・構いすぎて時間を溶かさないように、20回目以降は同じセリフに設定してます。・移動させることもできます。移動させた後に5...
『なんかよくわかんないやつの居るところ』というページを作ってみました。・場所はサイドバーの右下のほう(スマホだとページの下のほう)の座布団の画像をクリック(こちらからもいけます 👉️ なんかよくわかんないやつの居るところ)・17:00〜翌4:59のいわゆる夜だけ“やつ”を構うことができます。・キャラクターをクリックorタップすると、ただただセリフが出るだけのページです。・構いすぎて時間を溶かさないように、20回目以降は同じセリフに設定してます。・移動させることもできます。移動させた後に5... -
【お知らせ】おみくじページ作ってみました
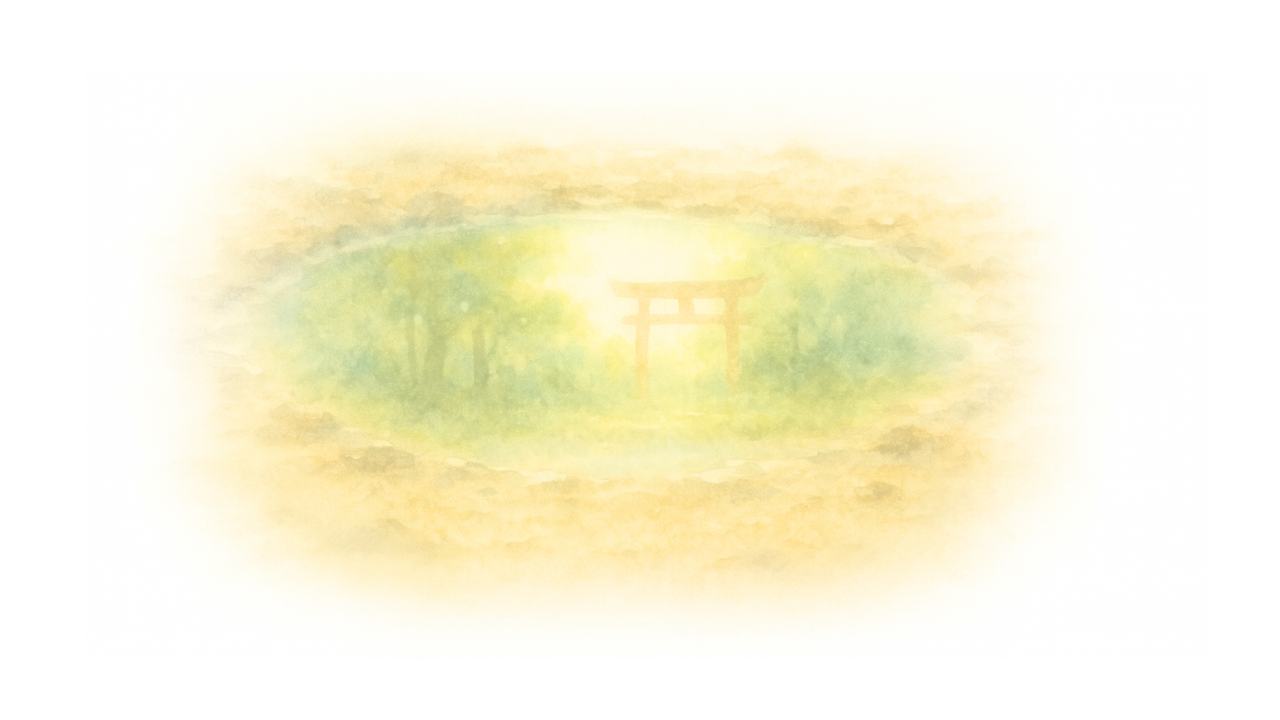 皆さま、いつも遊びに来てくださりありがとうございます!さてさて、ちょっとした新しいページを作成してみましたのでご案内です。 おみくじページを作ってみたので、ぜひ遊んでみてくださいね!・場所はトップページの下のほうの水たまりの画像をクリック (こちらからも行けます 👉️ 灯水鏡の杜 )・スクロールに合わせて動くアニメーション(?)にしています・1日1回しか引けず、1度引くとその日は再アクセスしても同じページには辿り着けない仕様 (昼と夜とで違うページに飛ぶようにしてみました) こう...
皆さま、いつも遊びに来てくださりありがとうございます!さてさて、ちょっとした新しいページを作成してみましたのでご案内です。 おみくじページを作ってみたので、ぜひ遊んでみてくださいね!・場所はトップページの下のほうの水たまりの画像をクリック (こちらからも行けます 👉️ 灯水鏡の杜 )・スクロールに合わせて動くアニメーション(?)にしています・1日1回しか引けず、1度引くとその日は再アクセスしても同じページには辿り着けない仕様 (昼と夜とで違うページに飛ぶようにしてみました) こう...
.webp)