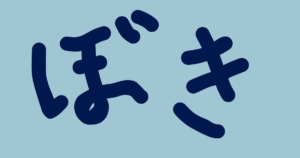会社を退職すると、失業保険や健康保険、税金など、さまざまな手続きを進める必要があります。しかし、何をどの順番でやればいいのか分からず、不安を感じる人も多いのではないでしょうか?
私も退職を経験して色々と手こずる部分がありました。
そこで今回は、退職後にやるべきことを7つのステップに分けて解説 します。これを読めば、手続きの漏れを防ぎ、スムーズに退職後の生活を整えることができるはずです。
退職後すぐにやるべき手続き①:失業保険

失業保険(雇用保険)の申請方法と注意点
退職後、次の仕事を探す予定がある場合は、ハローワークで失業保険(基本手当) の申請をしましょう。これは、雇用保険に一定期間加入していた人が、仕事を失った際に受け取れる給付金です。
失業保険を受給するための条件
失業保険を受け取るには、以下の条件を満たしている必要があります。
✅ 雇用保険に12カ月以上加入している(自己都合退職の場合)
✅ 働く意思と能力がある(すぐに就職する意思があることが必要)
✅ ハローワークで求職活動を行う(最低2回の就職活動実績が必要)
※ 会社都合退職(倒産・リストラ・パワハラ退職など)の場合は、6か月以上の雇用保険加入で受給可能。
失業保険の手続き方法(流れ)
会社から「離職票」を受け取る
退職後、1~2週間以内に会社から「離職票」が送られてきます。これがないとハローワークで手続きできないので、届かない場合は会社に確認しましょう。
ハローワークで失業保険の申請
離職票を受け取ったら、住所地を管轄するハローワークへ行き、失業保険の申請手続き を行います。
✅ 持ち物
- 離職票(会社からもらう)
- マイナンバーカード or 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- 通帳 or キャッシュカード(振込先口座の確認)
- 証明写真(3×2.5cm)2枚 → マイナンバーカードがあれば省略できるようです
- ハローワーク指定の求職申込書(窓口で記入)
申請後、ハローワークの説明会(雇用保険受給説明会)に参加する必要があります。
7日間の待機期間がある
申請が終わると、最初の7日間は「待機期間」 になります。この期間中は一切働けません。(アルバイトをすると待機期間がリセットされるので注意)
受給開始までの期間
- 自己都合退職 → 待機期間7日 + 給付制限期間(2か月)後に支給開始
- 会社都合退職 → 待機期間7日後、すぐに支給開始
2025年4月からは自己都合退職における給付制限期間が1か月になるようです。
失業認定を受ける(4週間ごとに報告)
ハローワークに行き、4週間に1回「失業認定」を受ける必要があります。
このとき、2回以上の就職活動実績 を報告しなければなりません。
✅ 就職活動実績に認められるもの
- ハローワークでの求人相談
- 転職フェアやセミナーの参加
- 書類応募や面接(ただしバイト応募は不可)
- 就職に関係する資格試験受験や受講
失業認定を受けないと給付がストップしてしまうので、必ずスケジュールを確認しておきましょう。
失業保険の支給額はどれくらい?
基本手当日額(1日あたりの給付額) は、退職前6か月の平均月収の約50~80% です。
✅ 目安となる支給額(1日あたり)
| 退職前の月収 | 失業保険の支給額(概算) |
|---|---|
| 20万円 | 約5,000円/日(約15万円/月) |
| 30万円 | 約6,800円/日(約20万円/月) |
| 40万円 | 約7,500円/日(約22万円/月) |
※ 年齢や雇用保険の加入年数によって変わります。
失業保険を早くもらう方法:再就職手当を活用!
もし、失業保険を受給中に就職が決まった場合、「再就職手当」 という制度を活用できます。
✅ 再就職手当とは?
失業保険の支給日数を残した状態で早期に再就職すると、残りの給付額の最大70% が一括で受け取れる制度です。
✅ 受給条件
- 失業保険の支給日数が3分の1以上残っていること
- 1年以上の雇用見込みがある仕事に就職すること
- 過去3年以内に再就職手当をもらっていないこと
✅ 再就職手当の計算例
- 失業保険の支給残り日数が100日
- 1日あたりの失業保険が6,000円
100日 × 6,000円 × 70% = 42万円 → 就職するだけで42万円が一括支給される!
再就職手当は大きなメリットがあるので、「少しでも早く仕事を見つけたい」と考えている人は、積極的に活用しましょう。
まとめ:失業保険を受け取るまでの流れ
- 会社から「離職票」を受け取る
- ハローワークで申請する(必要書類を準備)
- 7日間の待機期間を過ごす(この間は働けない)
- 自己都合退職なら2か月の給付制限がある(会社都合ならすぐ支給開始)
- 4週間ごとに失業認定を受ける(求職活動が必要)
- 失業保険を受給 or 早期に再就職した場合は「再就職手当」を申請
失業保険は、ただ申請すればもらえるものではなく、手続きや条件があるため、計画的に進めることが重要です。特に、再就職手当の制度を上手に活用すれば、よりスムーズに次の仕事へ移行できるので、転職活動と並行してチェックしておきましょう!
退職後すぐにやるべき手続き②:健康保険

退職後の健康保険の切り替えと手続き方法
会社を退職すると、それまで加入していた会社の健康保険が使えなくなるため、新たに健康保険に加入する必要があります。
しかし、健康保険の選択肢はいくつかあり、どの方法が最適なのかを判断することが重要 です。
健康保険の選択肢は3つ!どれを選ぶべき?
退職後の健康保険は、次の3つから選択することになります。
| 選択肢 | 特徴 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| ① 任意継続 | 会社の健康保険をそのまま継続(最大2年) | 会社の健康保険のほうが国保より安い場合 |
| ② 国民健康保険(国保) | 住んでいる自治体の国保に加入 | 退職前の収入が高い人、扶養に入れない人 |
| ③ 家族の扶養に入る | 配偶者や親の社会保険に加入 | 収入が年間130万円(または106万円)未満の人 |
どの健康保険を選ぶべきかは、保険料(毎月の支払い額)や条件を比較して決める のがポイントです。
1. 任意継続(会社の健康保険を続ける)
「任意継続」とは、退職後も引き続き会社の健康保険に加入できる制度 です。
最長で2年間 継続できますが、保険料は全額自己負担(会社負担分なし) になります。
任意継続のメリット・デメリット
◎ メリット
- 会社の健康保険が継続できるので安心
- 扶養家族も引き続き保険に入れる(保険料追加なし)
- 国保より保険料が安い場合がある(退職前の給与が低い人ほど有利)
✕ デメリット
- 会社が負担していた分も自己負担になるため、保険料が2倍に
- 退職後20日以内に手続きしないと加入できない
- 2年間は途中で解約できない(再就職時を除く)
任意継続の保険料の計算方法
✅ 保険料 = 退職前の標準報酬月額 × 健康保険料率(全額自己負担)
例えば、退職前の給与が月30万円 だった場合、
✅ 会社員時代の保険料(例:1万5,000円) → 退職後は2倍の3万円に
退職前の給与が高いと保険料も高くなるので、国保と比較して安いほうを選ぶのがポイント です。
任意継続の手続き方法
✅ 申請期限:退職後20日以内
✅ 手続き場所:退職前に加入していた健康保険組合 or 全国健康保険協会(協会けんぽ)
✅ 必要書類
- 任意継続被保険者資格取得申出書(健康保険組合 or 協会けんぽのHPでダウンロード)
- 健康保険証(退職前のもの)
- 本人確認書類(運転免許証など)
※ 2年間の継続が前提なので、途中でやめられない点に注意!
2. 国民健康保険(国保)に加入する
退職後、任意継続をしない場合は、住んでいる自治体の国民健康保険(国保)に加入する必要があります。
国民皆保険制度に基づき、任意継続を選ばない又は扶養に入らない場合には自ずと、こちらに加入することになるため、メリットやデメリットの表記は記載しておりません。
国民健康保険の保険料の計算方法
✅ 前年の年収 × 保険料率 + 均等割(定額負担)
例えば、前年の年収が400万円 だった場合、
✅ 国保の保険料 → 年間40万円(約3万3,000円/月)になることも
住んでいる自治体によって保険料が異なるので、市区町村の国保担当窓口で確認することが重要 です。
国保の手続き方法
✅ 申請期限:退職後14日以内
✅ 手続き場所:住んでいる市区町村の役所・役場
✅ 必要書類
- 退職日のわかる書類(離職票、退職証明書など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
3. 家族の扶養に入る(社会保険の被扶養者になる)
退職後、配偶者や親の社会保険に入れる場合は、「被扶養者」として加入 することも可能です。
扶養に入るための条件
✅ 年間収入が130万円未満(60歳以上は180万円未満)
✅ 扶養する家族(配偶者・親など)の社会保険に加入できる
✅ 配偶者や親の収入の2分の1未満であること
扶養に入るメリット・デメリット
◎ メリット
- 保険料の負担なし(無料で加入できる)
- 任意継続や国保より圧倒的にお得
✕ デメリット
- 年収130万円を超えると扶養から外れるため注意が必要
- フリーランスや個人事業主になる場合は基本的に扶養に入れない
扶養の手続き方法
✅ 申請期限:退職後すぐ(早めの申請が必要)
✅ 手続き場所:配偶者 or 親の勤務先の健康保険窓口
✅ 必要書類
- 退職日を証明する書類(離職票、退職証明書など)
- 被扶養者申請書(加入する健康保険の指定フォーマット)
まとめ:どの健康保険を選ぶべき?
| 健康保険の選択肢 | こんな人におすすめ |
|---|---|
| 任意継続 | 退職前の健康保険が安い or 扶養家族がいる |
| 国民健康保険 | 退職前の給与が高かった or 短期間の無職期間がある |
| 扶養に入る | 年収130万円未満で、家族の社会保険に加入できる |
健康保険の切り替えは退職後14日以内 に手続きが必要なので、早めに比較して最適な方法を選びましょう!
退職後すぐにやるべき手続き③:年金

退職後の年金の切り替えと手続き方法
会社を退職すると、それまで加入していた厚生年金(会社の年金制度) から、国民年金(自営業や無職の人向けの年金) に切り替える必要があります。
しかし、「年金の支払いが厳しい」「何を手続きすればいいのか分からない」と不安を感じる方も多いかもしれません。
ここでは、退職後の年金手続きをわかりやすく解説 します。
年金の選択肢は3つ!どれを選ぶべき?
退職後の年金は、以下の3つの方法から選びます。
| 選択肢 | 特徴 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| ① 国民年金に加入(第1号被保険者)〈基本の手続き〉 | 自営業・無職の人が加入する年金制度 | 退職後、再就職しない・フリーランスになる人 |
| ② 家族の扶養(第3号被保険者) | 配偶者(厚生年金加入者)の扶養に入る | 年収130万円未満で、配偶者の扶養に入れる人 |
| ③ 再就職して厚生年金に再加入 | 会社員として再就職すれば自動で加入 | 退職後すぐに新しい会社で働く人 |
退職後も年金の未納期間が発生しないように、早めにどの方法を選ぶか決めることが重要 です。
1.国民年金に加入する(基本の手続き)
会社員時代は厚生年金に加入していましたが、退職すると国民年金に切り替える 必要があります。
国民年金の支払い額(2024年度)
✅ 月額:16,520円(全員一律)
✅ 年間:198,240円
厚生年金と比べると支払額は減りますが、会社の負担分がなくなるため、将来の年金額も減る ことに注意が必要です。
国民年金の手続き方法
✅ 申請期限:退職後14日以内
✅ 手続き場所:住んでいる市区町村の役所・役場
✅ 必要書類
- 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
- 退職日のわかる書類(離職票、退職証明書など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
手続きをしないと、年金の未納期間が発生し、将来受け取る年金額が減るリスクがある ため、忘れずに申請しましょう。
年金の支払いが厳しい場合の救済制度
退職後すぐに収入がない場合、国民年金の支払いが厳しい こともあります。その場合、免除制度や猶予制度 を活用できます。
✅ ① 国民年金保険料の免除制度(支払額が減る or 0円になる)
前年の年収に応じて、以下の4段階の免除が受けられます。
| 免除の種類 | 支払額 |
|---|---|
| 全額免除 | 0円(支払い不要) |
| 3/4免除 | 4,130円/月 |
| 半額免除 | 8,260円/月 |
| 1/4免除 | 12,390円/月 |
✅ ② 納付猶予制度(50歳未満の人向け)
- 一時的に支払いを先延ばしできる
- 10年以内なら後払い(追納)も可能
ポイント:免除制度を使っても年金は将来の受給額に反映される
(全額免除の場合、年金の2分の1は支給される)
✅ ③ 学生納付特例(20歳以上の学生向け)
- 学生は年金の支払いを猶予できる制度(所得制限あり)
2.家族の扶養(第3号被保険者)に入る
配偶者(厚生年金加入者)の扶養に入れる場合、国民年金の支払いが不要 になります。
扶養に入るための条件
✅ 年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)
✅ 配偶者が厚生年金に加入している
✅ 配偶者の収入の半分以下である
✅ 手続き方法
✅ 申請期限:退職後すぐ(早めの申請が必要)
✅ 手続き場所:配偶者の勤務先の社会保険窓口
✅ 必要書類
- 退職日を証明する書類(離職票、退職証明書など)
- 扶養申請書(配偶者の勤務先で入手)
ポイント:扶養に入れると年金の支払いがゼロになるので、最もお得な選択肢
3.再就職する場合は厚生年金に再加入
✅ 会社員として再就職した場合
- 自動的に厚生年金に加入(手続き不要)
- 国民年金よりも将来の受給額が増える
✅ フリーランス・個人事業主になる場合
- 国民年金のみの加入(厚生年金なし)
- iDeCo(個人型確定拠出年金)を活用して年金を増やすのがおすすめ
iDeCo(個人型確定拠出年金)を活用する
退職後に厚生年金がなくなると、将来の年金額が減るため、自分で老後資金を準備する必要があります。また、企業型確定拠出年金を運用していた場合には、iDeCo口座への資金の移動も忘れずに!!
✅ iDeCoの特徴
- 掛金が全額所得控除(節税効果が大きい)
- 運用次第で資産が増える可能性がある
- 60歳まで引き出せないが、老後資金を確実に確保できる
✅ 掛金の上限
| 加入者の区分 | 掛金の上限(月額) |
|---|---|
| 自営業・フリーランス | 6.8万円 |
| 会社員(企業年金なし) | 2.3万円 |
| 会社員(企業型DCあり) | 2.0万円 |
フリーランスや自営業の人は、iDeCoを活用すると将来の年金を増やしながら節税メリットも得られる ので、ぜひ検討してみましょう。
まとめ:どの年金の選択肢を選ぶべき?
| 年金の選択肢 | こんな人におすすめ |
|---|---|
| 国民年金 | 退職後しばらく無職・フリーランスになる |
| 免除・猶予制度の利用 | 収入がなく、年金の支払いが厳しい |
| 扶養に入る | 年収130万円未満で、配偶者の扶養に入れる |
| 再就職(厚生年金) | 退職後すぐに新しい会社に勤める |
| iDeCoを活用 | 自営業・フリーランスで老後資金を増やしたい |
年金の切り替え手続きは退職後14日以内 に行い、将来のために適切な選択をしましょう!
退職後の税金の手続きと支払い方法(住民税・所得税)

会社を退職すると、住民税・所得税の支払い方法が変わる ため、手続きをしないと滞納や延滞金のリスクが発生します。退職後の税金は、どのように支払うのか、どんな場合に確定申告が必要か をしっかり確認しておきましょう。
住民税の支払い方法(会社員から個人納付へ)
住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、退職後もしばらく支払いが続きます。
(例:2024年に退職 → 2023年の所得に対する住民税を支払う必要あり)
✅ 住民税の支払い方法は2種類
| 支払い方法 | 特徴 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| 特別徴収(一括徴収) | 退職時に、未払いの住民税を給与から天引き(一括払い) | すぐに再就職する予定がない人 |
| 普通徴収 | 退職後、自分で自治体からの納付書を使って支払う | 分割払いを希望する人 |
✅ どの支払い方法になるかは、退職時のタイミングによる
| 退職時期 | 住民税の支払い方法 |
|---|---|
| 1~5月に退職 | 退職時に一括徴収(特別徴収) |
| 6~12月に退職 | 原則、普通徴収(納付書払い)に切り替え |
✅ 普通徴収になった場合の支払い方法
- 自治体から送られてくる納付書を使って支払う(コンビニ・銀行・ネットバンキング)
- 一括 or 4回の分割払い(6月・8月・10月・1月)を選択可能
住民税を滞納するとどうなる?
住民税を支払わないと、延滞金が発生し、最悪の場合は財産の差し押さえ もあり得ます。
支払いが厳しい場合は、自治体に相談すれば分割払い(猶予制度)を利用できる こともあるので、早めに対応しましょう。
退職後の所得税の手続き(確定申告が必要な場合)
退職時、会社が「年末調整」をしてくれる場合は確定申告不要 ですが、以下のケースでは確定申告が必要になります。
✅ 確定申告が必要なケース
| ケース | 説明 |
|---|---|
| 年の途中で退職し、年末調整を受けていない | 退職後に収入がない場合、所得税の還付を受けられる可能性あり |
| 退職金の税金が引かれすぎた場合 | 退職金の「退職所得控除」が適用されているか確認する |
| 退職後に副業や投資で収入があった場合 | 給与所得以外に年間20万円以上の所得があると確定申告が必要 |
| ふるさと納税をしており、ワンストップ特例が適用できない | 退職後に転職しない場合、ワンストップ特例が無効になり確定申告が必要 |
✅ 確定申告の期限
- 申告期間:翌年2月16日~3月15日(2025年の場合、2025年2月17日(月)~3月17日(月))
✅ 確定申告の手続き方法
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」 で申告書を作成
- e-Taxでオンライン申請 または税務署に郵送・持参
- 還付金が発生する場合は、1か月ほどで口座に振り込まれる
退職金の税金の仕組みと控除額
退職金を受け取った場合、「退職所得控除」 を適用することで、税金を抑えることができます。
✅ 退職所得控除額の計算方法
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数 |
| 20年以上 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 – 20年) |
✅ 退職金の課税対象額の計算方法
(退職金 – 退職所得控除)× 1/2 = 課税対象額
✅ 退職金の税金を節約する方法
- 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すると、源泉徴収額が減る
- 確定申告をすることで、払いすぎた税金の還付を受けられることがある
退職後に税金の負担を軽減する方法
退職後に収入がない場合、税金の支払いを減らす方法 もあります。
✅ 住民税の減免制度を利用する
- 自治体に申請すれば、収入が減った人向けの減免制度を適用できる場合がある
✅ 退職後に収入がない場合、住民税の分割納付を交渉する
- 自治体の窓口で「分割払いの相談」をすることで、支払い負担を減らせる
まとめ:退職後の税金のチェックリスト
✅ 住民税の支払い方法を確認(特別徴収 or 普通徴収)
✅ 確定申告が必要かどうか確認(副業・退職金・ふるさと納税など)
✅ 退職金の税金を抑えるために「退職所得控除」を適用する
✅ 税金の負担が大きい場合は、減免や分割払いの相談をする
退職後は税金の支払いを忘れがちですが、滞納すると延滞金が発生するので注意が必要です。
住民税・所得税の負担を軽減する方法を活用し、賢く管理していきましょう!
仕事探しや再就職の準備(転職活動・再就職支援)

退職後に再就職を考えている場合、転職活動を計画的に進めることが大切 です。
「どこで求人を探すのがいい?」「転職活動のコツは?」と悩む方のために、効率よく仕事を見つける方法 を詳しく解説します。
仕事探しの選択肢(どんな働き方を選ぶ?)
再就職の方法は大きく分けて3つあります。
| 選択肢 | 特徴 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| ① 正社員として転職 | 安定した収入・社会保険完備 | 安定を求める、キャリアを積みたい |
| ② 派遣・契約社員 | 短期間で仕事を見つけやすい | すぐに働きたい、フルタイムは厳しい |
| ③ フリーランス・個人事業主 | 自由な働き方・収入が不安定 | スキルを活かして独立したい |
✅ 再就職した場合 → 厚生年金・社会保険に加入できる
✅ フリーランスの場合 → 国民年金・国民健康保険に加入する必要あり
まずは、自分がどの働き方を選びたいのかを明確にすることが大切です。
転職活動の進め方(成功するための5ステップ)
① 自分の希望条件を整理する
まずは、以下の項目についてどんな条件を優先するのか を明確にしましょう。
✅ 勤務地(リモートワークOKか?通勤時間はどれくらいまで?)
✅ 給与(最低限必要な年収はいくらか?)
✅ 仕事内容(業界・職種・企業の規模など)
✅ 勤務時間・休日(フルタイム・時短・週休2日など)
② 求人を探す(どこで探す?)
✅ ハローワーク(公的機関で安心、地元企業の求人が多い)
➡ https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
✅ 転職エージェント(無料でサポートを受けられる)
➡ リクルートエージェント、doda、マイナビ転職、JACリクルートメントなど
✅ 転職サイト(自分のペースで探せる)
➡ リクナビNEXT、Indeed、エン転職など
✅ 派遣会社を活用する(すぐに働きたい人向け)
➡ テンプスタッフ、スタッフサービス、パソナなど
✅ 企業の公式サイトから応募(気になる企業がある場合)
ポイント:複数の方法を併用し、幅広く情報を集めると効率的!
転職活動のコツ(書類・面接対策)
① 履歴書・職務経歴書の作成ポイント
✅ 履歴書
- 自己PRや志望動機は「応募企業向け」にカスタマイズする
- 空白期間がある場合は理由を明確に(スキル習得・資格取得など)
- 誤字脱字を防ぐために、第三者にチェックしてもらう
✅ 職務経歴書
- これまでの経験を「成果ベース」でアピールする(売上UP、コスト削減など)
- 業務内容ではなく「自分の強み・工夫したこと」を具体的に書く
- 転職エージェントに添削を依頼するのもおすすめ
② 面接対策(よく聞かれる質問と回答例)
✅ 「前職を辞めた理由は?」
➡ ネガティブな理由ではなく、前向きな転職理由を伝える
✅ 「志望動機は?」
➡ 企業の強みと自分のスキルを関連づけて説明する
✅ 「退職後の期間は何をしていましたか?」
➡ 「資格取得・スキルアップのための時間を使っていました」と説明すると好印象
ポイント:事前に回答を準備し、できれば模擬面接を受けると自信がつく!
失業保険をもらいながら転職活動する方法
✅ 失業保険を受給中の求職活動のルール
- 4週間ごとにハローワークで失業認定を受ける
- 2回以上の求職活動実績が必要(応募、面接、セミナー参加など)
- アルバイトは申告が必要(週20時間以上は給付停止の可能性)
✅ 再就職手当を活用する
- 失業保険の受給中に就職が決まると、最大70%の手当が一括支給される
- 一定の条件(1年以上の雇用見込みなど)を満たす必要がある
失業保険を活用しながら、計画的に転職活動を進めましょう!
再就職しない場合の選択肢(副業・フリーランス)
✅ クラウドワーク(在宅で仕事を受ける)
➡ ランサーズ、クラウドワークス、ココナラ
✅ スキルを活かした仕事(専門職向け)
➡ ITエンジニア(フリーランスエージェント利用)
➡ Webデザイン・ライティング(SNSやブログ運営)
✅ アルバイトやパートで収入を得る
➡ 失業保険を受給しながら短時間のアルバイトをする
✅ 資格を取得して新たなキャリアを築く
➡ 簿記、FP、ITパスポート、宅建など
フリーランスや副業で収入を得る場合、税金や年金の手続きが変わるため注意が必要 です。

まとめ:仕事探しの進め方チェックリスト
✅ 希望条件を整理する(給与・勤務地・業種など)
✅ 転職サイト・エージェント・ハローワークを活用する
✅ 履歴書・職務経歴書を準備し、面接対策をする
✅ 失業保険を受給しながら転職活動を進める
✅ 再就職が決まったら「再就職手当」を活用する
まとめ
退職後は、健康保険・年金・税金の手続き や 再就職の準備 など、やるべきことが多くあります。
手続きを怠ると、未納や延滞金の発生、将来の年金受給額の減少などのリスク もあるため、早めに対応することが重要 です。
退職後にやることチェックリスト
退職後すぐにやるべき手続き(健康保険・年金・失業保険)
✅ 健康保険の切り替え(任意継続 / 国民健康保険 / 扶養)(退職後14日以内)
✅ 年金の切り替え(国民年金 / 扶養 / 免除制度の申請)(退職後14日以内)
✅ 失業保険の申請(ハローワークで手続き)(退職後すぐ)
退職後の税金の手続き(住民税・所得税)
✅ 住民税の支払い方法を確認(特別徴収 or 普通徴収)
✅ 確定申告が必要か確認(退職金・副業・ふるさと納税など)
退職金の確認と資産運用
✅ 退職金の税金を減らすために「退職所得控除」を適用する
✅ NISA・iDeCoなどで老後資金の運用を考える
仕事探しや再就職の準備
✅ 転職サイト・エージェント・ハローワークを活用する
✅ 履歴書・職務経歴書を準備し、面接対策をする
✅ 再就職が決まったら「再就職手当」を活用する
退職後の生活をスムーズにするポイント
✔ 期限がある手続き(健康保険・年金・失業保険)は早めに対応する
✔ 税金の負担を減らすために、確定申告や分割払いを活用する
✔ 転職活動は複数の方法を組み合わせて効率よく進める
✔ 再就職が決まらない場合は、副業やフリーランスも視野に入れる
これらの手続きを計画的に進めることで、退職後の生活をスムーズに移行できます。
よくある質問
Q1. 退職後、すぐにやるべき最優先の手続きは?
A. 健康保険・年金の切り替えが最優先です。
退職後14日以内に「健康保険の切り替え」と 「年金の切り替え」 をしないと、未加入期間が発生してしまう可能性があります。
また、すぐに再就職しない場合は、ハローワークで失業保険の申請 をしておくと、給付を受けることができます。失業保険を受給する場合には、ハローワークは早めに行ったほうが良いです。
Q2. 退職後に税金を滞納するとどうなる?
A. 延滞金が発生し、最悪の場合は財産の差し押さえがあります。
特に住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、退職後もしばらく支払いが続きます。支払いが厳しい場合は、自治体に相談して分割払いを申請することが可能 です。
国民年金も、ですね…。
Q3. 退職後のブランクが長いと転職に不利になる?
A. ブランクの期間をどう活用したかが重要です。
「資格取得」「スキルアップ」「自己学習」「ボランティア活動」など、前向きな活動をしていたことを伝えればマイナスにはなりません。
また、職務経歴書に「ブランク期間に行ったこと」を記載すると、企業側に良い印象を与えられます。
Q4. 失業保険を受給中にアルバイトをするとどうなる?
A. 週20時間以上働くと、失業保険がストップする可能性があります。
アルバイトや副業をする場合、ハローワークに申告する必要があります。
週20時間未満であれば、一部減額されながら受給できるケースもある ため、ハローワークで確認するのがおすすめです。
.webp)